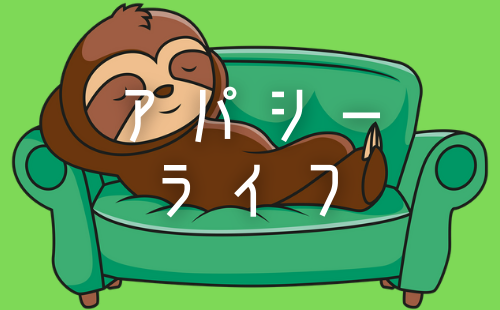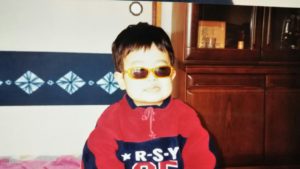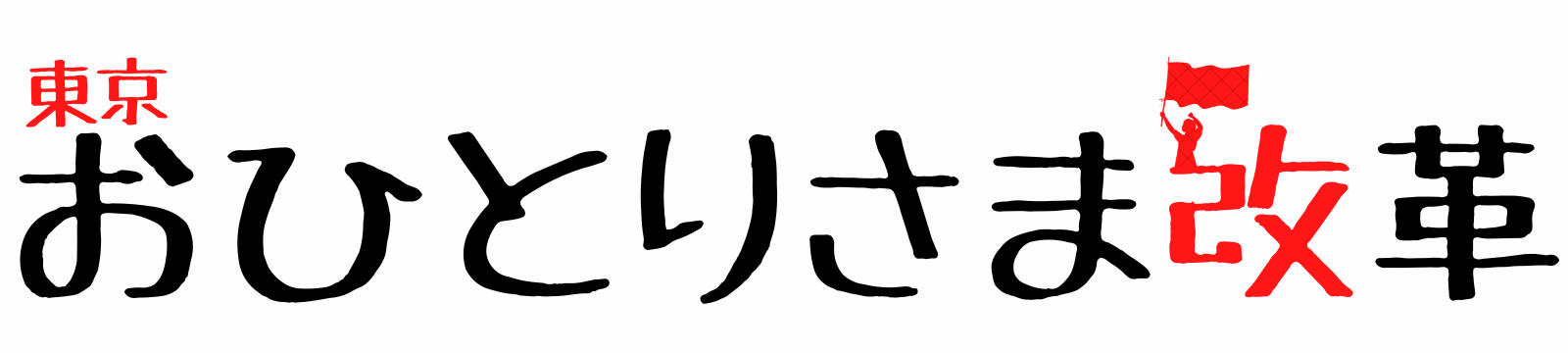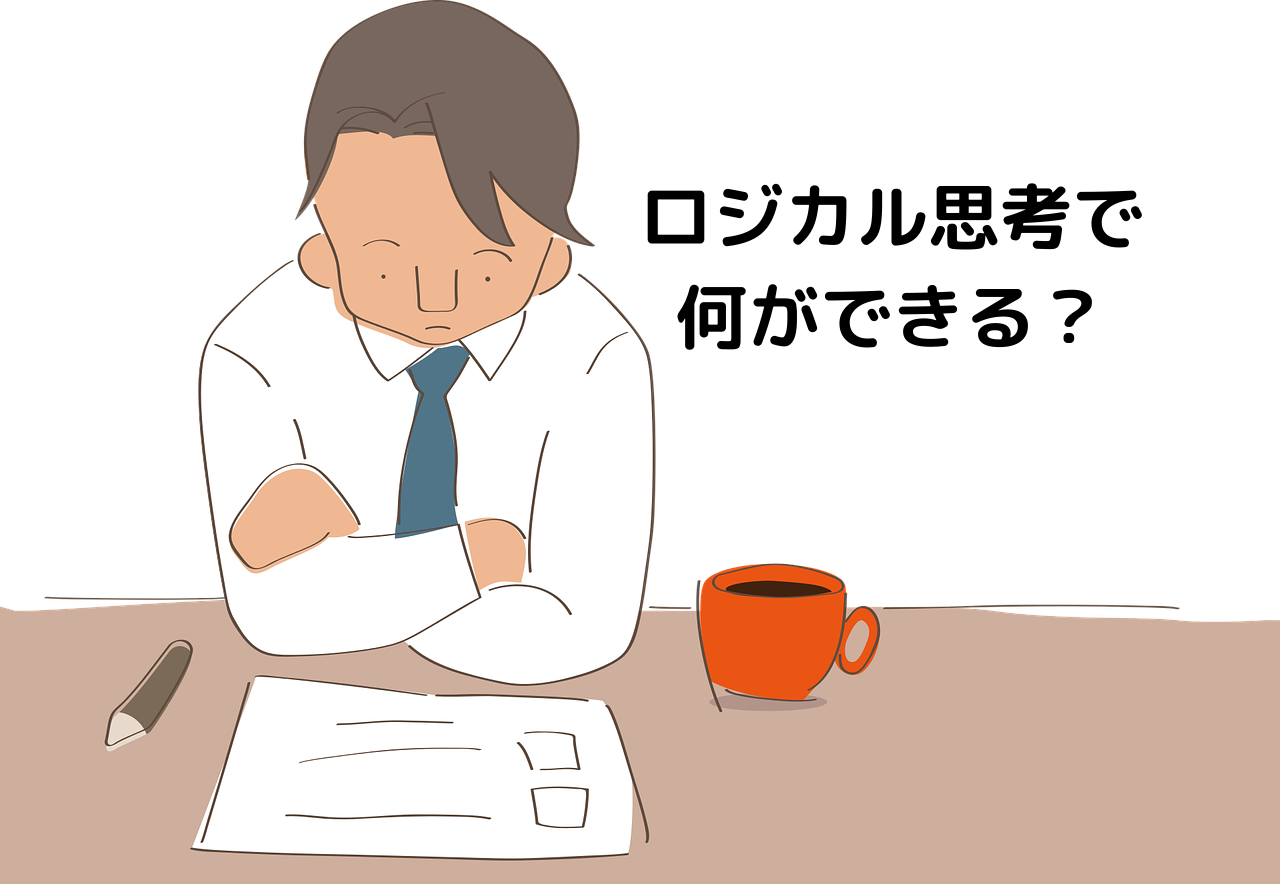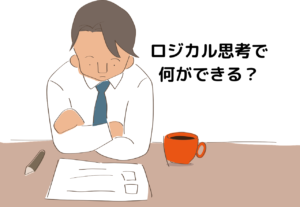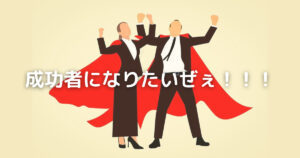人から「何を言いたいのかわからない」「結論を先に言え」と言われる。
長く話をしていて「そういえば、何の話してたっけ」と思うことがある。
さらに、
文章を書くとき制限字数を守って書くことができない。
本や新聞などを速く読もうと思ってもすごく時間がかかってしまう。
みたいな経験ありませんか?
これらはロジカル思考力の低さによるものです。
ロジカル思考には一定の考え方、思考パターンがあります。
それらを使い続けると、だんだん慣れてきて、どういう場面でどういう考え方、思考パターンを使えばいいのかがわかってきます。
今回は、ロジカル思考を身につけることによるメリットと、ロジカル思考の限界について解説します。
ロジカル思考とは
物事の筋道のことをロジックといい、物事の筋道が通っている状態のことを「ロジカル」であるという言い方をします。
ここでは、ロジカル思考を次のように定義します。
ロジカル思考=物事を道筋立てて考えること
筋道が通っている状態とは、物事の関係や構造がはっきりしている状態ともいえます。
したがって、ロジカル思考とは、さまざまな物事の関係性を整理したり、物事の全体がどのような構造で成り立っているのか明らかにしていくことでもあります。
物事の関係性や構造を明確にすることは、全体像を把握したり、本質を深く理解したりすることにつながります。
また、筋道が通ることによって、第三者が違和感を覚えない、客観的で妥当性が高い状態を生み出します。
相手とのコミュニケーションを図る際にも、自分の主張を分かりやすく説明できるようになり、スムーズに理解してもらえます。
より良い仕事をしていく上では、ただ考えるのではなく、ロジカルに考えることが欠かせないのです。
ロジカル思考の5つのメリット
ロジカル思考力を身につけることによって、ビジネスを進める上でどのようなメリットが得られるのでしょうか。
ここでは、5つのメリットを紹介します。
- 筋道の通った主張ができる
- 事象間の関係が明確になる
- 情報を整理し、構造化できる
- 合理的な推論ができる
- イシューを把握できる
筋道の通った主張ができる
筋道の通った主張ができるようになります。
ビジネスではさまざまな場面で、意見を言ったり、説得したりすることがあります。
自分が正しいと思っていることでも、感覚で物を言ったり、感情に任せて思いをぶつけたりしても、それが相手に伝わるとは限りません。
主張したい内容をロジカルに整理していくことで、話の筋道が通りやすくなりますし、内容に妥当性や客観性が生まれます。
直ちに賛同までは得られないかもしれませんが、少なくとも相手に意図が明確に伝わりますし、納得感をもって話を聞いてもらえるはずです。
事象間の関係が明確になる
事象間の関係を明確にすることができます。
例えば、何か問題に直面し、これを解決するためには、起きているさまざまな事象を分析し、望ましくない事象の原因となっている事象は何かなど、事象間の関係性を見いだす必要があります。
しかし、複雑な問題であればあるほど、1つ1つの事象の関係性を明らかにしてくことが難しくなります。
このような場面で、ロジカルに物事を見ていくことで、それぞれの事象がどのような関係で影響を及ぼし合っているのかをつかむことができます。
情報を整理し、構造化できる
情報を整理し、構造化することができます。
さまざまな情報が得られたとき、個々の情報にとらわれても全体的に漠然と眺めていても、本質を見落としてしまいます。
ある事柄についてどういった要素がどのように関連し合って成り立っているのか、構造化して捉える必要があります。
合理的な推論ができる
合理的な推論で、確度の高い仮説を導き出すことができます。
何かを発想するとき、思い付きで突拍子もない仮説を出したとしても、その確度はまちまちです。
物事をロジカルに分析し、かつ、自分の知識や情報を組み合わせて推論することで、確度が高く、価値の高い仮説を導き出すことができるのです。
イシューを把握できる
議論の際、イシューを把握することができます。
イシューとは、議論などで最終的に明らかにしたい事柄のことをいいます。
議論を行っていると、時に、論点が大きく横道にそれてしまうことがあります。
それは、議論のメンバーがイシューを意識していないことから起こります。
話の筋をロジカルに分析することで、イシューを正確につかむことができます。
それにより、議論を有効なものにし、明快な結論を導き出すことができます。
以上のように、ロジカル思考力を身につけ、実践することで、ビジネスの成果につながっていきます。
ロジカル思考の限界
ここまでロジカル思考の内容とメリットについて学んできましたが、ロジカル思考によって全てがうまくいくわけではありません。
ここからは、ロジカル思考の限界について3点指摘しておきます。
ロジカルなら必ず正しいとは限らない
ロジカルであったとしても、それが主張内容の正当性を常に保証するとは限りません。
低所得者には生活保護が支給されているが、これは「人類は平等」という大原則に反する。
生活保護制度を廃止するべきである。
この例は、話の筋道が通っている点ではロジカルだといえます。
ただ、「人類は平等」とは別に、「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」という憲法で保障された原則があります。
2つの原則のうち、政府は後者を価値基準として重視し、生活保護制度を導入しています。
ロジカルであることと内容の正しさは本来は一致するはずですが、この例のように、そうはならない場合があります。
このような場合は、筋道が通っているかどうかよりも、どういう価値基準を重視しているかに目を向けて、主張内容の正しさを判断すべきです。
特にこの例のように、一見ロジカルなようではあっても受け入れ難い主張がなされている場合、往々にして価値基準が妥当性にかけているものです。
提示された主張がどのような価値基準に拠っているのか、吟味するようにしましょう。
ロジカル思考が独創的なアイデアに結び付くとは限らない
思考がロジカルであれば、独創的なアイデアに結びつくかというと、必ずしもそうではありません。
過去の偉大な発明や発見を振り返ると、必ずしもロジカル思考によって得られたものばかりではありません。
むしろ、あるとき偶然にひらめくことが多いようです。
このようなひらめきを得るためには道筋や構造にとらわれない自由な発想が必要です。
正しい結論よりも斬新なアイデアが求められるようなときにはあえて道筋にこだわらず、自由な発想を心がけることも大切です。
ロジカルなら説得できるとは限らない
私たちはロジカル思考を駆使することによって、話の説得力が増すことを期待します。
ただし、説得力は、ロジカルさだけで決まるわけではありません。
あなたが迷った末に買ったものを1つ思い出してください。
どうして、あなたはその商品を買ったのでしょうか。
例えば、生命保険に加入したとしたら、販売員の説明がロジカルだったからでしょうか。
新刊書籍だったら、ネットの書評がロジカルだったからでしょうか。
おそらく、ロジカルさに加え、場の雰囲気であったり、販売員の人柄であったり、好きか嫌いかという気持ちなど、さまざまな要因が作用したことでしょう。
つまり、話の説得力は、内容のロジカルさだけでなく、相手との共感、信頼、個々人の価値観といった要因にも大きく左右されます。
自分が何かを主張して相手を説得する場合は、このことをよく心得ておきましょう。
よく「私の意見は正論なのだから」と持論を一方的に振りかざし、相手を力ずくで説得しようとする人がいますが、あまり効果はありません。
ロジカルな主張を心がけると同時に、相手の立場を思いやる、自分の人間性を分かってもらう、相手の価値観を理解するといった配慮が大切です。
まとめ
以上、ロジカル思考の内容とメリット、ロジカル思考の限界について解説しました。
- ロジカル思考とは、物事を道筋立てて考えることである。
- ロジカル思考を身につけると、「筋道の通った主張ができる」「事象間の関係が明確になる」「情報を整理し、構造化できる」「合理的な推論ができる」「イシューを把握できる」というメリットがある。
- ロジカル思考には、「ロジカルなら必ず正しいとは限らない」「ロジカル思考が独創的なアイデアに結び付くとは限らない」「ロジカルなら説得できるとは限らない」という限界がある。
日常生活においては“繰り返して起こる事柄”が多くを占めるため、さほど真剣に考えなくても困ることはないでしょう。
しかし、ビジネスを取り巻く環境は大きく変化しており、従来の経験則に頼ってなんとなく考えているようでは成果をあげることが難しくなってきました。
このような状況において求められるのが、論理的に物事を捉え、考えるロジカル思考力なのです。