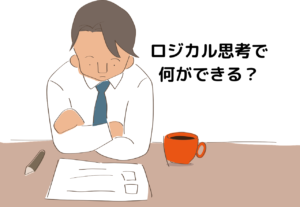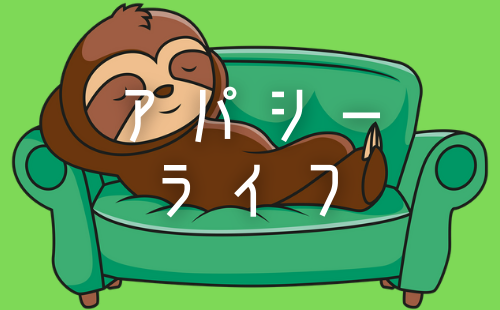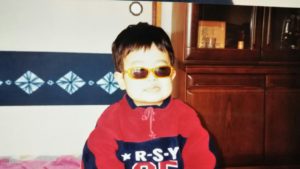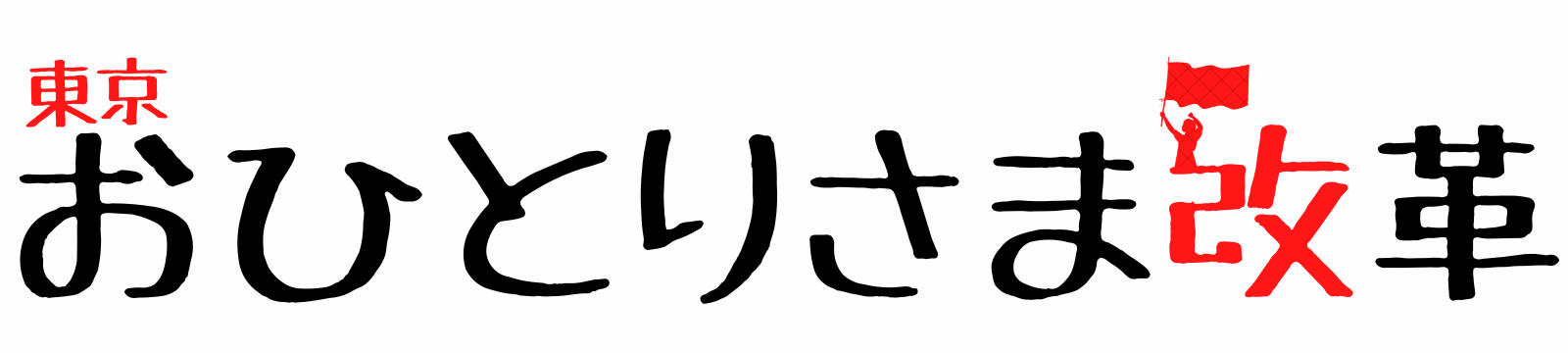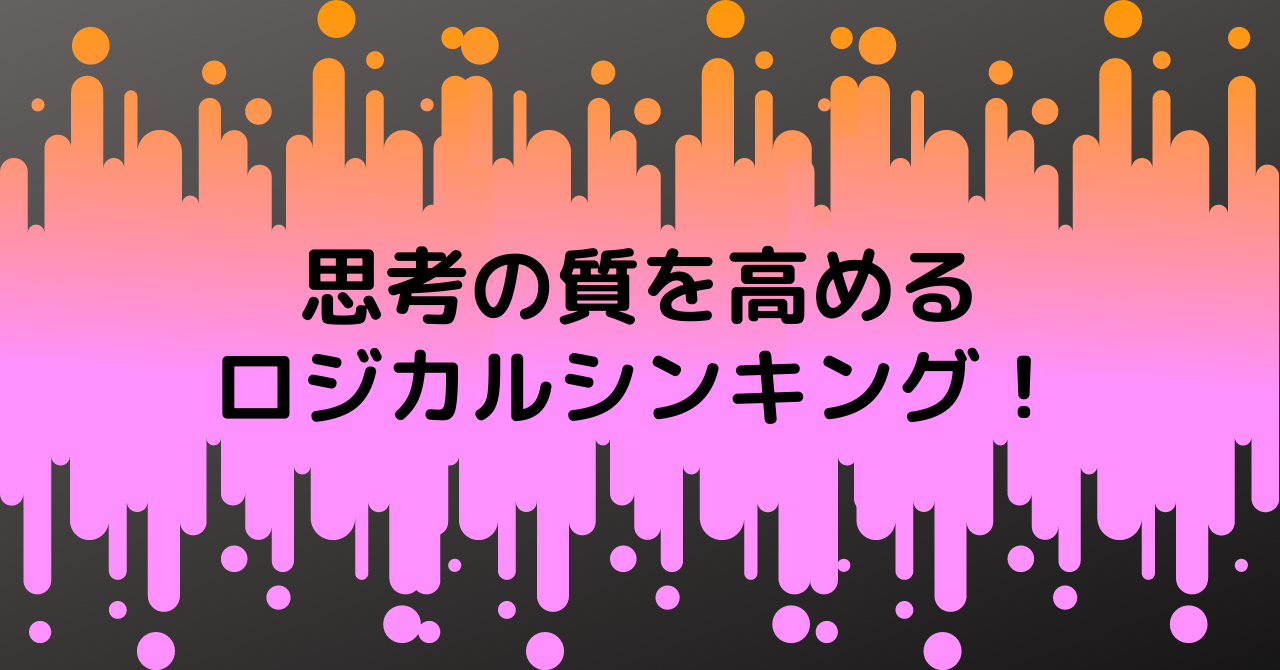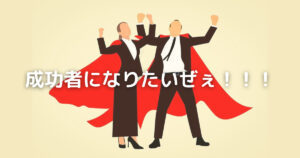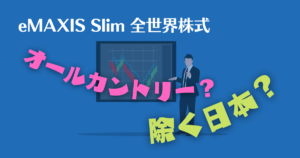決まったことを決まったように行う・・・。
そこから新しいビジネスチャンスを見出すことはできません。
まずは、自分たちの取り巻いている物事の「前提」や「常識」、そして、それらから派生した「結論」を疑ってみることが大切です。
情報量と思考量との意外な関係
情報量が増えることは素晴らしいことだと考えていませんか?
ところが、情報の増加が思考量の低下を招くことがあるのです。
情報は、問題を分析して解決していくための指針を示してくれる大切な要素です。
したがって、情報の量が増えるほど、様々な問題を解決するための方法も増えていきます。
しかし、情報量の増加は、蓄積した情報内容の整理に多大な労力を要するという状況を招きます。
その結果、溢れかえった情報を個々に検証するための思考力が低下し、本来、問題を解決するための手段だった情報が自分の考えに思えてきます。
つまり、情報に全てを決められてしまうことになるのです。
といっても、情報は、生きていく上でなくてはならないものです。
そこで、思考量の減少という状況に陥らないために必要になるのが、「ロジカルシンキング」です。
様々な情報を客観的に整理して、頭の中で優先順位をつけて正しく活用することで、過労による思考の低下を抑え、情報量の氾濫に惑わされることがなくなります。
なおかつ十分に分析された情報を活かして、ビジネスパーソンとして、より幅広い問題解決の能力を身につけることができるようになるのです。
徹底した懐疑論者になる
「前提」や「常識」によって生じた「結論」に囲まれて多くに人は生きています。
それらを疑い、思考の質を高めることで、新たな視点が生まれてくるのです。
決まったことを決まったように行う・・・。
そこから新しいビジネスチャンスを見出すことはできません。
まずは、自分たちを取り巻いている物事の「前提」や「常識」、そして、それらから派生した「結論」を疑ってみることです。
まず、「前提」や「常識」から一度離れて、それ以外に方法がないかどうか検証してみましょう。
不可能と思い込んでいたことや無駄だと考えていたものにチャンスが隠れているかもしれません。
俯瞰して物事を見てみれば、誰も着目しなかった発見があるのです。
ビジネスでは、「あちらを立てればこちらが立たない」というような問題を克服していかなくてはならない状況にぶつかります。
しかし、そこに至るまでの「結論」を疑うことで、思考の質はさらに高まります。
隠れていた問題がひとつひとつ明らかになり、新たな解決策が生まれるきっかけになることも少なくありません。
「前提」に無理がある場合や「常識」が間違っていることに気づくケースもあります。
クリティカル(※1)な視点を養っていきましょう。
隠れた構造を明らかにする
すべての現象には、それを生み出した構造=システムが隠されています。
構造を理解することで、物事の本質がわかり、問題の解決につながるのです。
順調に業績を伸ばしている企業があるとします。
一見、健全な経営状態と思われていたのに、突然成長がストップして、やがて破綻に至るケースは少なくありません。
その原因は、好調に見えていた状況に隠れた部分=構造に歪みが生じているからにほかなりません。
小さな歪みが、やがて、構造全体に影響を及ぼして致命傷となるわけです。
この隠れた構造を理解しない限り、常に大きなリスクを抱えてビジネスを展開していくことになるといえます。
原因と結果という現象は、必ずしも時間的・空間的に近接してはいません。
構造に生じた無理な負荷がさらに別の要因を生んで、思いもしない場所で破綻の端緒となっていることもあります。
しかし、それぞれのつながりを理解していれば、現在発生している問題の構造を早い段階で知ることができます。
そうすれば、現象が抱えている構造の歪みなどについて様々な対策を講じることが可能となり、大きな問題が発生する前に解決できるポイントが見えてくるのです。
ミクロとマクロの眼を持つ
物事の詳細を観察するミクロの眼と、もっと離れた視点で全体像を見渡して考えるマクロの眼。
2つの眼を使い分けることで見落としがなくなります。
店頭で商品の並べ方を工夫したり、工場で生産ライン(※2)の効率化を考えるなど、いわば現場に近接したミクロな視点は、ビジネスにおいて欠かせない大切な基本事項です。
そこから顧客の消費を促す新しいアイデアや、生産力アップのシステムが生まれてくるのですから。
それでは、ちょっと考え方を変えて、現場から離れたマクロな視点で全体を見渡してみましょう。
今度は、近くでは気付かなかった問題点や原因、向上可能なポイントを俯瞰して発見することができます。
現場では様々な出来事が絶えず起きており、それらに対応しながら生産の向上を図っていると、ミクロな眼は培われますが、全体の構造が見えなくなっていきます。
そんなときにあえて高空から景色を眺めるようにマクロな眼で全体を見ると、思いがけない発見や問題の解決ができます。
店舗の売り場や工場内から離れることで、建物の改装や人事の構成を考えたり、工場の立地や生産システムそのものを変更することに思い至るなど、近くにいては思いつかない改善点を見出せます。
グラフをうまく活用する
数学の授業で習ったことがあるX軸とY軸のグラフを覚えていますか?
このグラフを物事の考え方に当てはめることで、たくさんのメリットが生まれます。
横軸をX、縦軸をY で表すシンプルなグラフに自分の考えを置き換えてみましょう。
グラフのもとは数式です。
数式には曖昧さの入る余地はありjません。
つまり、考え方のグラフということは、全ての要因や現象を可視化することであり、迷いや希望的観測といった不確定要素を排除することにもなります。
ビジネスにおいては、常に自分の直面している現象をグラフ化して考えるように心がけておきましょう。
どのようなときも客観的に物事を判断できるようになります。
自分の考えや調査内容を、第三者に正しく伝えるのにもグラフ化は効果的です。
例えば、X軸を時間の経過、Y軸を市場の大きさと考て、経過した時間と市場の動向との関連性を解析することで、どの時期にどういうマーケティング戦略(※3)を用いるかを具体的に説明できるようになります。
どの時期に資金投入を開始して、市場拡大を行うか、成長予想や衰退の時期までをイメージして伝えることができるのです。
時間と空間という厳密な因果関係(※4)を数式化した論理は、大きな説得力を持ちます。
偽の相関を見抜く
実際には因果関係がないのに、間違った相関によって大きな勘違いをしてしまうことがあります。
隠れている錯誤の罠をチェックしましょう。
「結論ありき」の考え方は、一見関係がありそうで、実は全く関連性がない、いわゆる「擬似相関」に騙される危険性があります。
2つの現象によって導かれたと考えられる「結論」に、別の要素が影響を及ぼしている可能性を見落としているかもしれないのです。
そのまま原因や理由を間違ったまま物事を進めてしまうと、予想もしなかったトラブルへ発展するリスクが高まります。
結論に至るまでの因果関係をもう一度検証して、正しい相関関係を導くことが大切です。
擬似相関で一番見落としやすいのが、第三の原因の存在です。
例えばチョコレートの販売数が2月に上昇しているデータがあります。
一見、「2月はチョコレートが売れる」という結論が成立しそうですが、第三の原因として「バレンタインデー」というイベントが存在します。
つまり、チョコレートの売上は2月半ばまでしか上昇せず、それ以降に増産したら大きな損失を出すということです。
まずは結論を疑い、その構造が正しいのかどうか考え直してみましょう。
思考停止ワードに気をつける
わかったつもりになるキーワードに要注意。
流行語や経済用語などに隠れている響きのいい言葉によって、思考力が止まってしまうことがあるのです。
よく意味はわからないけれど、耳に心地よくてなんとなく使っている言葉があります。
昔なら感じを多用した言葉で、最近では横文字が多くなっていると思います。
それはビジネスの世界でも同じです。
経済用語などでよく使われるそれらのキーワードが会議などでもよく出てきますが、なんとなくわかった気になったり、知らないのが恥ずかしいと思ってスルーすることで、説明の意図を正確に理解できない危険性が出てきます。
つまり、「思考停止」の状態に陥ってしまうのです。
いわゆる「思考停止ワード」が出てきたら要注意です。
具体性が求められる場で抽象的な内容がまかり通ってしまうのでは、のちのち企業戦略(※5)や会社運営に悪影響を及ぼします。
そういう場合は「たとえば?」と確認してみるのが効果的な対処方法です。
具体例を挙げさせることで、本来の議論の場に全体を引き戻すことができます。
また、「・・・を挽回する」「・・・を再考する」など動詞の思考停止ワードも存在します。
これは「誰が」「何を」「いつ」「どうやって」と基本的な説明を求めることで解決できます。
一般解ではなく個別解を探る
ビジネスには複雑な要素が絡みます。
そこで適切な答えを導くには、何にでも当てはまる一般解ではなく、その問題だけを指す個別解を探す必要があります。
一般解とは、「主語」を替えてみても成立する解答のことです。
主語の「私」を「あなた」「彼」「○○さん」に替えても違和感のない場合は、一般解だといえます。
例えば「私は営業が得意です」とAさんが言ったとします。
でも「私」を別の主語に入れ替えても違和感は感じられません。
ではAさんが「私は毎日50件の新規訪問をして一日平均10件の商談を成立させ、営業部でもトップの成績です」と述べたらどうでしょう?
これはAさんにしか通用しない答えです。
これが個別解です。
ビジネスにおいて、一般解と個別解の差は極めて大きいといえます。
一般解では教科書的ともいえる無難でどうとでも取れる抽象的な内容しか伝えることができないからです。
それに対して個別解は、具体性があるため、導き出された解答に説得力が生まれます。
相手もまた、具体的な内容や情報を得て、円滑なコミュニケーションが生まれていくのです。
つまり、いろいろな状況に応じて自分だけの個別解を作れる人が優秀なビジネスマンといえるわけです。
コラム:「ロジハラ」にご用心!
パワハラやモラハラに続き、近頃は新たなハラスメントとして「ロジハラ」が話題になっています。
例えば、仕事を進めるにあたり、正論で押し通そうとするような人は、相手が不快感や嫌悪感を覚え、ハラスメントに当たるというのです。
普段、ビジネスの現場でロジカルシンキングを実践している人は相手を説得するために、順序立てて丁寧に論理的に説明したのに、それがハラスメントに当たると言われたらさぞかしショックでしょう。
人によっては正論であればあるほど(特にそれが自分に都合の悪い正論であるなら)、不快に思う人がいるのは事実です。
しかし、だからといって、萎縮してせっかく身につけたロジカルシンキングを使わないのはもったいないことですし、ビジネスがスムーズに進まなくなってしまいます。
ロジハラと言われるのを避けるには、相手やその時の状況によって、臨機応変に話し方や声のトーンを変えることです。
同じことを述べていても、言い方が高圧的かそうでないかで、相手の受け取り方は違ってきます。
大事なのは話しながら常に相手の反応を確かめることではないでしょうか。