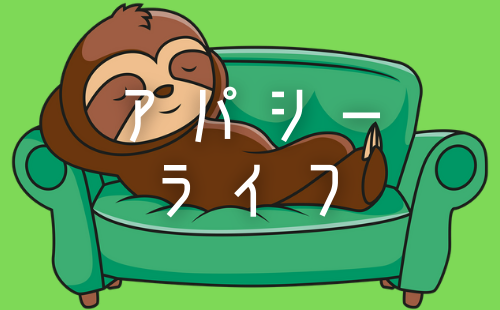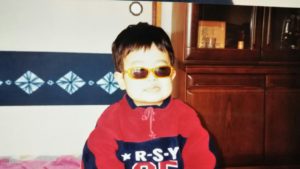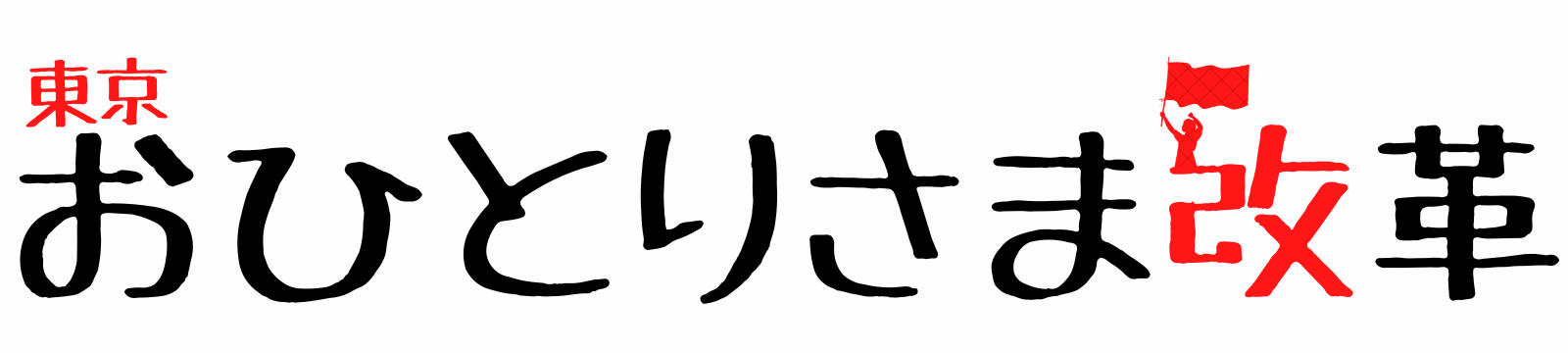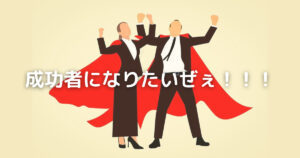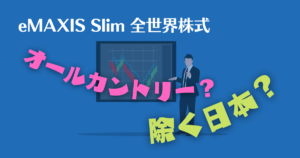「ロジカルシンキングを鍛えたいけどどうすればいいんだろう。」
ロジカルシンキングを鍛えるには「トロッコ問題」や「テセウスの船」、「アキレスと亀」などの有名な思考実験で脳を訓練することが有効です。
ここでは様々な思考実験についてご紹介します。
トロッコ問題

論理的思考を高めるのに、思考実験を行うのは有効です。
代表的なのはトロッコ問題。
多数を助けるために少数を犠牲にするのは正しいのでしょうか。
思考実験の代表「トロッコ問題」とは、イギリスの倫理学者フットが提案したものです。
暴走するトロッコが線路を走っています。
この線路の先には5人の作業員がいて、このままではぶつかり5人が死んでしまいます。
一方、その途中に線路の切り替えスイッチがあり、その地点にあなたが立っています。
線路を切り替えて別の軌道に替えれば5人が助かります。
しかし別の線路には1人の作業員がいます。
つまりスイッチを切り替えれば5人が助かり1人が死ぬ。
切り替えなければ1人が助かり5人が死ぬ。
どちらを選ぶべきでしょうか。
この問題に正解はありません。
5人を助けるという意見は、功利主義の「最大多数の最大幸福(※1)」に近い考えです。
一方、1人を助けるという意見には、スイッチを切り替えた場合、1人を明確な意志をもって殺すことになるのを避けるという意義があります。
テセウスの船

思考実験には「テセウスの船」もあります。
新しい材料によって置き換えられたものの同一性(アイデンティティ(※2))を問う問題です。
「テセウスの船」は、古代ギリシアのパラドックス。
アテネで造られたこの船は、傷んだ部分を何度も新しい木材に取り替え続けて、最終的にすべて新しい木材から構成される形で残りました。
これを本物のテセウスの船と呼べるでしょうか。
さらに厄介なことに職人が、取り替えられた朽ちた木材を使って、もうひとつのテセウスの船を作りました。
ボロボロですぐに沈むような船です。
しかし使われている木材はオリジナルの素材です。
この復元された船と、修理された船のどちらが本物でしょうか。
修理船はオリジナルと同じ機能を持ちます。
また、偽物だとしたら複数回の修理をした船のどの時期をもって偽物になったのでしょう。
一方復元船は、のちの歴史家が見た場合こちらを本物としがちです。
このように判断基準によって異なってきます。
アキレスと亀

アキレスと亀は、古代ギリシア・ゼノンのパラドックス。
俊足の若者アキレスが亀に絶対に追いつけないのはなぜでしょう。
俊足の若者アキレスは亀と競争しました。
ただし、スタート地点はアキレスの方が亀より少し後ろです。
この競争はどうなるでしょうか。
普通に考えれば、俊足のアキレスが簡単に亀を追い抜いてゴールするはずです。
しかしこの思考実験ではそうはなりません。
亀のスタート地点をA点としましょう。
その少し先をB点、さらにその先をC点・・・と考えてみます。
両者ともにスタートします。
アキレスがA点に達します。
しかしそのときには亀も遅いながらも先に進んでいるのでA点にはおらずB点に達しています。
さらにアキレスがB点に達したとき、今度は亀はC点に達しています。
これを延々と繰り返します。
したがってアキレスは絶対に亀に追いつけない。
これは、アキレスと亀の関係に視点を絞っているために成立するパラドックスなのです。
誕生日のパラドックス

30人のクラスがあります。
この30人の中で同じ誕生日の人がいる可能性は何%でしょう。
パラドックスだけに意外な答えが出てきます。
30人からなるクラスで、同じ誕生日の人が出てくる可能性は普通に考えると低くなります。
1年366日(うるう日含む)だとして、30/366で8%でしょうか?
しかし、これは正しい確率計算をすれば自然と確かな数字が出てきます。
これは、誰も誕生日が被らない確率を計算し、それを1から引くことで導き出されます。
まずAさんは1/366。次にBさんがそれと被らない確率が365/366。CさんがAさんBさんと被らないのが364/366。こうやって30人全員の確率を出して、それをすべて掛け合わせれば、誰も被らない確率が出ます。
計算すると0.294。
これを1から引けば0.706。
つまり同じ誕生日がいる確率は70.6%になります。
意外に高いですよね。
我々がイメージする数値と、数学上の数値が異なる点がミソです。
チキンゲーム

チキンゲームとは、それぞれ車に乗った2人が向かい合い、猛スピードで走るもの。
避けなかった方が勝者です。
このゲームの攻略法は?
このゲームは4つに分けられます。
Aは自分が避けず、相手が避けるもの。
これは自分が勝ちます。
しかし相手が必ず避けるとは限りません。
お互い、相手が避けると思って正面衝突して死ぬのがBです。
Cは、Bを怖れ自分が避けるものです。
これは負けになり、チキン(臆病者)扱いされます。
でも死ぬより良いでしょう。
Dは共に避けるもの。
これは両者敗北になりますが命は助かります。
結局、相手は死にたくないと考え避けるはず→だから進む→だが相手も同じことを考え進むはず→ならば避ける。
よってDが最適な解になります。
ここで相手の意志がわかる占い師がいて、どちらかに同情したらどうでしょう。
相手の動向がわかるため同乗した方が勝ちそうです。
でも同乗しない方から考えると、自分が進めば死にたくない相手は必ず避けます。
よって同乗しない方が勝つのです。
ジャガイモのパラドックス

99%が水分で1%が固形部分のジャガイモが100kgあったとします。
ここから水分を1%減らしたらジャガイモは何kgになるでしょうか。
1%を減らしたのならば、水分が98%になり、100kgのジャガイモも99kgになりそうです。
しかしこれでは誤りです。
例えを変えましょう。
99%が女性、1%が男性で合計100人の会社があります。
ここで女性の比率が1%減って98%になったとき女性は何人になるでしょう。
98人では誤りです。
男性1人、女性98人では、女性比率が98%にならないのです。
女性比率を98%にするためには、女性が1人減り、男性が1人増えなくてはなりません。
しかしジャガイモの固形部分同様に、その分を増やさない(男性が増えない)のならば答えは変わります。
つまり女性が50人減って49人、男性1人で初めて98%になります。
同様にジャガイモも水分49kg、固形部分1kgで計50kgが解です。
この意外性がパラドックスの所以です。
臓器くじ

「臓器くじ」とは1人の犠牲で5人救えると仮定した思考実験です。
犠牲者より多くの人を救えるこのシステム、あなたは支持しますか?
病院には5人の患者がいます。
それぞれ別の臓器提供を待っており、提供がなければ長くありません。
そこへ男性が健康診断にやってきました。
彼を安楽死(※3)させてその臓器を5人に提供すれば、1人の犠牲で5人が助かります。
もちろん事前告知などをしないので、男性を恐怖に陥れることはありません。
臓器提供者をくじ引きで公平に決めるのはどうでしょう。
一見、多くの患者を救えるシステムに思えますが、ほとんどの人が反対するはずです。
より多くの人を救えるとしても、自分や大切な人が犠牲になる恐怖の方を強く感じ、意図的に誰かを殺す選択を避ける方が、人として論理的といえるのです。
やっかいな新提案

努力の成果が結ばれようとしたその寸前、より良いアイデアが出た場合、論理的思考を邪魔する“心理”が働きます。
あなたは新製品開発部の部長です。
あなたが企画し、進めてきたプロジェクトが3ヶ月後にいよいよ発売日を迎えようとしていました。
ところが部下の一人が新素材で商品の作り直しを提案してきました。
確かに新素材を使えば性能はさらに向上します。
発売スケジュールも現在のままで進められそうですが・・・。
既存のプロジェクトをリセットする選択は難しいものです。
それは、これまでの努力や費用・時間が簡単に覆されることへの抵抗感であったり、プロジェクトを進めてきた自身のプライドが原因です。
もちろん、完全に感情を排除することはできません。
大事なのは感情をコントロールすることでしょう。
特定保健用食品の偽装

自分の会社で不正が行われていたら、告発するのが当然。
その「当たり前」を行いにくくする、思考の動きを探ってみましょう。
一人の会社員が、特定保健用食品(※4)の認定を受けた自社商品の産地や製法が、いつの間にか違うものに変わっていたのに気づきました。
上司は「製法自体は違法じゃないし、栄養価も大差ない」と問題視していません。
当然告発すべき事案ですが、なかなか踏み切れない人が多いのが実情です。
これは消費者という広範囲への責任より、同僚や自分自身といった近い距離にあるものへの心配が勝ってしまうのが原因です。
また「内部告発」にマイナスイメージがあるのも要因でしょう。
選択に感情が影響するのは避けられませんが、視野を広くすることで論理的な選択肢を取りやすくなるはずです。
タイムマシン物語

タイムマシンで自由に未来や過去へ行けたら、とても夢のある話ですが、そこには矛盾が生じてしまう危険性が潜んでいます。
もし、タイムマシン(※5)で過去へ行き、なんらかの事象を改変した場合、現実にはどのような影響が出るのでしょうか。
例えば、タケシという男がいたとしましょう。
彼がまだ10歳の頃、当時5歳だった妹を病気で亡くしました。
それから20年後、妹の命を奪った病気の特効薬とタイムマシンを開発したタケシは、過去に遡って妹を病死の運命から救います。
未来は妹が生存するルートに沿って書き換えられるはずですが、そこには多くの矛盾、いわゆるタイムパラドックスが生じてきます。
妹の生存には未来のタケシの過去移動が必須ですが、妹が生存する世界では、タケシが特効薬を持って過去に移動を行う必要性はなくなるわけです。
だとしたら、一体誰が妹を助けてくれたというのでしょうか。
トランプの奇跡

たとえ同じ確率で起こりうる事象だとしても、その結果が特徴的だと、人間はそこに特別な意味を見出そうとしてしまいます。
あるところに、一人の女性がいました。
着ていく服のコーディネートに悩んでいた彼女は、ランダムに4枚のトランプを引き、その色の組み合わせ次第で着る服を決めようとしました。
すると、不思議なことに、4枚ともエースを引いてしまったのです。
奇跡とも思える結果に興奮した彼女にとって、もはや着ていく服の悩みなど、どうでもいいことのように思えました。
しかし、落ち着いて考えてみると、エースを4枚引いた場合も、全くバラバラのカードを引いた場合も、確率的には全く変わらないのです。
それなのに人間は、特徴的な結果を目の当たりにすると、それが奇跡のように錯覚してしまうのです。
これは、ルーレットで同じ結果が何十回も連続しては出にくいはずだと勘違いする「ギャンブラーの誤謬」と通じるところがあります。
抜き打ちテスト

いくら論理的な思考を心がけたとしても、与えられた情報を馬鹿正直に捉えるだけでは、思わぬ誤算が生まれることもあります。
あるところに、一人の男子高校生がいたとします。
彼は先生から「来週のどこかで抜き打ちテストを行う。当日にならないとその日にテストがあるかどうかわからないぞ」と言われました。
そこで、何事も論理的に考える癖のある彼は、あることに気がつきます。
「当日にならないとわからない状況を作り出すなら、最後の金曜日にテストが行われることはない」はずだと。
しかし、木曜が実質的な最終日だと考えると、金曜を最終日とした場合と同じ理論が成立し、今度は「木曜にテストが行われることはない」という考えに至ります。
この思考を繰り返した結果、彼は「どの曜日でも抜き打ちテストは実施不可」という答えにたどり着いてしまいました。
実際は水曜にテストが行われ、男子高校生は驚きましたが、彼の思考のどこに問題があったのでしょうか。
男子高校生の考え方の問題点
- 先生の「当日にならないとその日にテストがあるかわからないぞ」という発言を厳密に捉えすぎた。
- 先生の発言は単純に「来週のどこかでテストを行う」という程度の曖昧なものだったが、男子高校生は論理的思考にこだわるあまり、そのことに気付かなかった。
- 結果的に不意を打たれる形となり、抜き打ちテストを成立させてしまった。
共犯者の自白

2人の人間がお互いに利己的な思考をした結果、両者にとって不利益なはずの選択肢を取ってしまうケースがあります。
あるところに、AとBという人間がいました。
ある事件の容疑者である2人は、別々の部屋で取り調べを受けています。
口を割らない彼らに、取調官はこう持ちかけました。
「お前たちのそちらかが自白し、もう一方が黙秘したなら、自白した者を捜査協力者といて釈放し、黙秘した者を懲役10年とする。2人とも自白した場合は共に懲役6年。2人とも黙秘なら懲役2年だ。」
論理的、あるいは客観的にトータルの懲役年数で考えれば、2人とも黙秘した場合の計4年が最も少なくなります。
お互いに黙秘するのが最も賢い選択のように思えますが、AとBのそれぞれが出した答えは、共に「自白する」というものでした。
結果、2人は各6年、計12年もの懲役を受けることになってしまいますが、そこには「囚人のジレンマ」という問題があります。
コンピュータが支配する世界

未来すら予測しうる超高性能コンピュータが完成したとしたら、世の中の人々みんなが幸せになれるでしょうか。
遠い将来、人間の脳を完璧に解析したり、あらゆる情報をシミュレートして未来すら予測できるコンピュータが完成したとしましょう。
人々は自分の子どもの才能を分析させ、最も適した職業に就けるよう教育を施します。
就職採用も機械が行ってくれるのでミスマッチは起きませんし、婚活だって同様に、機械が最適な異性を探し出してくれます。
警察の捜査も、容疑者らしき人を見つけてきて、片っ端から機械で分析すればすぐに犯人がわかります。
犯罪率は下がり、将来的に犯罪を起こす可能性が高い人には、事前に更生プログラムを受けさせることができます。
物事が機械の均一な価値観で評価され、誰もが無駄な努力をせずに済む夢の世界。
しかし、見方を変えれば、人間性を否定したディストピアとも言えそうです。
コラム:ビジネスにおける論理的思考力を鍛えるためには「思考実験」は最適!

「トロッコ問題」や「テセウスの船」「アキレスと亀」といった思考実験。
思考実験とは、ある特定の条件の下で考えを深め、頭の中で推論を重ねながら自分なりの結論を導き出していく思考による実験ですが、これはビジネスパーソンがプレゼンや商談において論理を積み重ねながら相手を説得していく行為と極めてよく似ています。
例えば、消費財メーカーのビジネスパーソンが、ある新商品を売り出したいと考えていたとします。
このとき彼の頭の中には様々な方法が思い浮かんでは消えていきますが、このとき彼は無意識のうちに思考実験をしているのです。
それはこんな感じです。
「既存の当社の量販店チャンネルを利用してキャンペーンを打ちたいが、イマイチ新鮮味に欠ける。もし会議で役員にそのことを指摘されたら・・・」
「テレビCMを大々的に打って世間の認知度を高めるか・・・。しかし、予算に見合った効果が果たして期待できるか? 期待できるとしたらその根拠は?」
こうした営みは、まさに思考実験そのものと言えるでしょう。