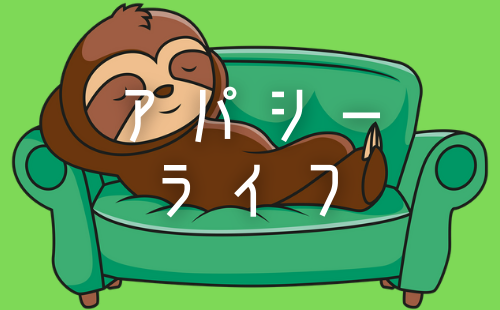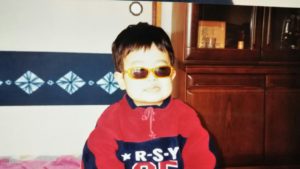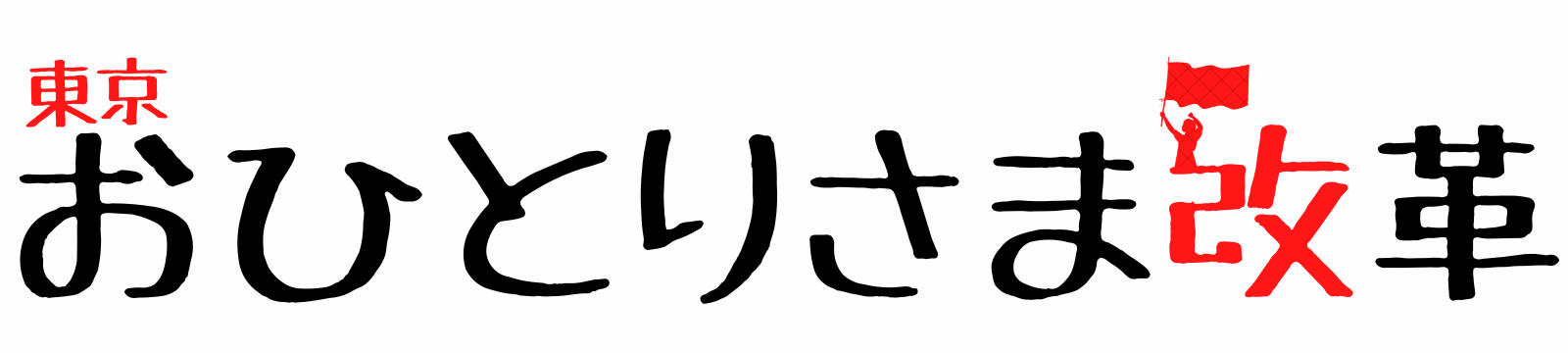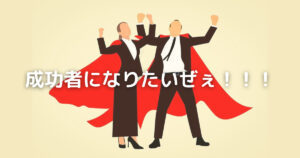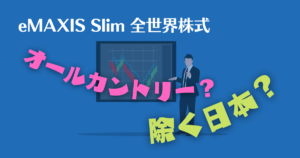ビジネスシーンにおいては常に結論部分とそれを導き出す根拠となった事象との関係を正しく把握することが大切。
そして、そのための技術が So What? と Why So? なのです。
あるべき姿と現状のギャップを認識して正しい問題設定をする
「現状」を踏まえて適切なギャップを設定しないと、到達不可能な「あるべき姿」に誘導されて状況が悪化する?
ビジネスもスポーツも、「現状」と「あるべき姿」のギャップを埋めるために努力を繰り返しています。
たとえば売上を150%にまで伸ばしたい、100メートル走のタイムを15秒から14秒にまで縮めたい、といった具合です。
しかし「現状」と「あるべき姿」を誤って設定してしまうと、途端にこのロジックは破綻してしまいます。
たとえば、「あるべき姿」を100メートルを7秒で走りたいと設定したとしましょう。
これはもう、実現不可能なギャップとして検討対象外と判断しなければいけません。
しかし現実世界では往々にして、この誤った設定をそのまま検証し、さらに非現実的な”正しそうに見える答え”が導き出されてしまうことがあります。
その誤りに気づかないと状況は悪くなる一方なので、常に適切な「あるべき姿」を見定めなければなりません。
問題可決の秘訣は「What」から「How」へ向かうこと
最初にWhatを考え、それを実現するためにHowを考えるのが、適切な目標設定のための重要な思考の順序です。
「現状」を踏まえた「あるべき姿」は、成績を向上させるうえで忘れることのできないひとつの指標です。
では、「あるべき姿」はどのような思考パターンで構築していけばよいのでしょうか。
このときに重要なのが、What(なにをすべきか)とHow(どうやって)の関係です。
ミスとしてありがちなのが最初にHowを考えてしまうパターン。
これでは、現状で実現可能な範囲の発想しかできず、結果的に容易な到達目標しか設定できませんから、達成できたとしても満足度は低いでしょう。
しかし最初にWhatをきちんと設定することで、それを実現するためのHowも正しく構築することができますし、今までになかった新しいHowを発見するかもしれません。
WhatからHowに進むプロセスはそれほど重要な意味を持っているのです。
問題と考えている「主語」を明確にする
ひとつの現象も、立場が変われば見え方も変わる。
常に問題点の主題を意識して分析することで、有効な解決策が導き出されます。
何か解決しなければならない問題があったとしましょう。
しかしその解決策を探る時、問題の本質が見えていないばかりに見当違いな解決策を模索してしまうことがあります。
ここでいう問題の本質とは、「主語」。
長らく続く低金利政策(※1)は住宅ローンを抱えているサラリーマンにとってはありがたい話ですが、資産家にとっては利息収入の減少という困った問題です。
ひとつの現象でも、主語の設定によって解釈は大きく異なってくるのです。
しかし、漫然と問題点を言語化している段階では、この「主語」の存在がはっきりしないケースが多いもの。
そのため、そこからピラミッド構造を構築しようとしても、有効な切り口が見つかりません。
ですから常に、項目を設定するときには問題点がどこにあるのか、誰の立場で問題なのかを意識しておく必要があるのです。
「80/20」の法則を利用する
100%の結果を求められない世界なら、20%の労力で80%の成果を得る選択肢のほうが生産性を高める?
「80/20(エイティ・トゥエンティ)の法則」と呼ばれるものがあります。
たとえば、売上の 80%が上位20%の製品であったり、テストで80点を取るまでは簡単だが百点を取るためにはその数倍の努力が必要になる、といった具合です。
これは総じて2割の努力で8割の結果を得ることができているということの証左です。
逆の視点で、要点の20%さえ押さえておけば80%の効果が得られるから、残りの20%の効果のために残りの80%の労力を割くのは費用対効果(※2)が低いと考えることもできます。
それよりも残りの80%のリソースをほかのことに振り分けるほうが生産性は高まるでしょう。
特にビジネスの世界は100点満点でなくても成立するケースが多く、学問のように完璧を求められるわけではありません。
よりスピーディで生産性を高めるための判断も必要なのです。
正しい答えにたどり着く鍵は「仮説」を持つこと
仮説を立てることで検証すべき対象が定まり、検証を重ねることで問題点を改めたり新たなテーマを構築することができます。
仮説は、当面の目標や結論と言い換えることができるかもしれません。
まずはこうした目標や結論を明示しておくことで、それを起点に情報収集や分析を行い、そこで得られたデータをもとに、より精度の高い目標や結論を再設定することができるのです。
「国内のX社を買収して中国へ進出してY事業を展開する」といった説があれば、なぜX社の買収が必要なのか、なぜ中国に進出するのか、Y事業にどんな伸び代があるのかなど、さまざまな観点から分析することができます。
その過程で得られたデータを根拠に、買収先をZ社に変更したり、進出先を別地域に再設定するなど、新しい方向性を見つけ出すこともできます。
しかし最初の仮説がないと、何かを検討する目的も根拠もなく、実りのない作業を延々と繰り返すことにつながってしまいます。
「仮説」を出発点として論点で構成されるピラミッド「イシューツリー」
仮説を検証する論点(イシュー)を構築することで、検証すべき論点そのものが明快になり、不要な要素が排除されます。
イシューツリーのピラミッドは、前項で触れた仮説Aが頂点のピラミッド構造になります。
そして直下に段には、仮説Aを検証するためのさまざまな疑問文のイシューBが置かれます。
「BだからAである」という論を逆説的に示していく構図です。
ここで仮説に関してYESかNOで答えることができるB1、B2、B3・・・という問いを重ね、YESが多く集まれば、結果的にAは正しいということになるわけです。
また、イシューBでは重要なポイントと考慮すべきではないポイントの切り分けが容易になり、見当違いの論点を排除して精度の高い結論を得ることもできるようになることもできます。
ロジカルに上流から下流に流れるピラミッド構造と比較するとBの段階で構築の難易度が高まりますが、その分問題解決のための重要な要素や視点が得られる思考法です。
最初の仮説にとらわれずに仮説をどんどん進化させる
当初の仮説や成功体験にとらわれず、状況の変化に合わせて柔軟に仮説を進化させていくことで停滞する状況から脱却できます。
状況を分析していくうえで、仮説の設定は欠かせません。
しかし、その仮説が正しいとは限らず、検証を重ねたうえで進化させていくことも重要です。
たとえば、「売上の中核をなす定番ブランド商品に注力していれば経営が安定する」という仮説を立てます。
しかし売上が下降線をたどりはじめたら、再検証が必要です。
原因として競合企業の新商品にシェアを奪われている、新しいブランドのブームが起こっているといった要素が浮上してきて、当初の仮説はNOの結論に至りました。
そんなときは「定番ブランドのみに依存した経営から脱却すべき」という新しい仮説を立て、そこからさらに分析を進めて「定番ブランドに加えてブームの商品も中核に据え、さらに新商品の開発も急務」という結論に至ります。
最初の仮説に固執せず柔軟に対応していく姿勢が必要なのです。
「なぜ」を5回繰り返すことで、問題を多面的に捉える
解決しなければならない問題に直面したときは、状況について「なぜ」と5回問いかけることで、多面的な視点で分析できます。
ひとつの課題や問いかけに対して、それを裏返した答えだけで解決したと錯覚してしまうときがあります。
「商品Aの売上が下がった」に、「売上を上げよう」という具合です。
これでは、単に方針を示しただけで、具体的な対策や分析が全く論じられていません。
商品Aが好調だったときの成功体験に影響されて、対症療法や安易な方針だけでつい安心してしまうのです。
そんなときは、課題や問いかけに必ず「なぜ」と付け加えるようにしましょう。
そうすれば、単に裏返しただけの答えは返ってきません。
ここでもし「商品Aが古びてきたからではないか」という答えが返ってきたら、次は「なぜ古びたのか」と問いを重ねます。
この「なぜ」を5回繰り返せば、おおむね本質的な問題点までたどり着けるはずです。
話の飛びをなくす技術 ーSo What? と Why So?
相手に話が通じないと悩む人は、自分の意見を述べる際、根拠と結論にしっかりとしたつながりがあるかどうか確認してみましょう。
誰かに自分の結論を説明するとき、私たちは「よって」「したがって」「このように」といった言葉を使いますが、こうしたワードの前後の話に矛盾や飛躍があると、相手に理解してもらえません。
そうした状況を避けるためには、日頃から根拠と結論の正しい関係を把握できる能力が必要です。
そのための技術が So What? と Why So? です。
So What? とは、判断の材料となる情報や事象から、「だからどうなのか?」という結論を抽出する作業です。
逆に Why So? は、すでに出されている結論から、「なぜそうなのか?」という根拠を抽出する作業です。
これができないと、結論と根拠をうまく結び付けられず、ディスコミュニケーション(※3)の原因となってしまいます。
So What? と Why So? を習慣化する
正しい結論を導き出せない、あるいは根拠を説明できないのは、日常的にそうした思考訓練を行なっていないからです。
仕事の効率が悪い人にありがちなのは、日常的な So What? と Why So? の習慣化ができておらず、人に何かを説明するのも、人の話から新しい情報を得たり推測したりするのも苦手という状態です。
こうした苦手を克服し、伝達力を高めるためには、日頃から地道に So What? と Why So? の作業を繰り返し、根拠と結論をつなげる訓練をしていくしかありません。
新聞や雑誌などを読むとき、判断の材料となる情報や事象を見かけたら、「So What?(だからどうなのか?)」と、結論を考える癖をつけましょう。
逆に、社説など誰かが出した結論を見かけたら、「Why So?(なぜそうなのか?)」と、根拠を考えましょう。
こうすることで物事の要点を素早く把握する能力が鍛えられ、迅速で円滑なコミュニケーションを行うことが可能になります。
「観察」の So What? と Why So?
So What? と Why So? を駆使すれば、情報や事象などの材料から得られる要点をまとめ、相手に向けて正確に説明することができます。
So What? と Why So? の応用法には、大きく分けて「観察」と「洞察」という2つの要素に分けることができます。
たとえば、同じデータを見ていたとしても、人はそれぞれ違った内容を読み取ることがあります。
事実認識の段階で齟齬が生じてしまうと、その後の議論が噛み合わず、時間を無駄にすることになります。
そこで役立つのが「観察」の So What? と Why So? です。
グラフなどのデータを表す図表を見るときは、まず、その図表からどんな課題が読み取れるのかを、So What?(だからどうなのか?)によって解き明かし、周囲と共有しましょう。
複数の図表がある場合は、ひとつずつ課題を確認していきます。最後にすべての図表から得られた課題を要約して結論を出し、Why So?(なぜそうなのか?)によって検証すればよいのです。
「洞察」の So What? と Why So?
事実を正しく認識・共有したら、次はそこからさらなる So What? と Why So? を実施して、新たな情報を導き出しましょう。
So What? と Why So? の応用法の2つ目は「洞察」です。
「洞察」の So What? と Why So? を駆使すれば、ある状況を示す複数のデータを分析し、そこから一定のルールや法則といった新たな情報を得たり、自分たちが受けるであろう影響や、今後取るべき方針を導き出すことができます。
仮説を導き出す行為も、「洞察」の So What? と Why So? の一種と言えます。
「洞察」の So What? と Why So? を実施するにあたっては、まず「観察」と同様、課題(テーマ)の把握と個々の分析を行います。
次に「洞察」の So What? によって個々の分析結果から法則性を導き出すわけですが、重要なのは、導き出された法則性が本当に正しいかどうか、「洞察」の Why So? できちんと検証を行うことです。
算数問題で検算を行うのと同じですね。
So What? と Why So? 、True?を繰り返す癖をつける
構築されたピラミッド構造は的確なものなのか。
それを検証するために有効なのが、Why So? と So What? 、True? の問いかけです。
ピラミッド構造の精度がどれくらいのものかは、一見しただけではわかりません。
ピラミッド構造を構築したときは、最後に全体を俯瞰して検証してみる必要があるのです。
そこで有効なのが、Why So? と So What? 、True? という問いかけです。
Why So? は「なぜそうなのか?」と言い換えることができ、ピラミッドの頂点から下流に分岐する項目の妥当性を検証できます。
逆に下流からは So What?「だからなに?」という問いかけで、複数の項目(理由)から上流の項目(結論)が的確かを見極めます。
True? はまさに「本当に?」で、最終的な結論や各項目の情報そのものの精度を問います。
この作業により、ピラミッド構造全体の精度が高まり、新たな問題の発見につながることもあります。
論理のパターンを理解する① 並列型
So What? と Why So? を使った論理の基本を学んだら、あとは実践的な論理構成を組み立てましょう?
実践的な論理構成の代表として並列型があります。
結論を頂点にその下の階層に複数の根拠が並列されて並んでいます。
これらの根拠はMECE(モレ・重複・ズレがない)の関係で構造化されています。
また、縦方向においては、So What? / Why So?(結局どういうことなのか? / なぜそのようなことが言えるのか?)の関係で階層化されています。
これをたとえば、販売チャネル(※4)に商品を供給している消費財メーカーの事例で見てみましょう。
消費財(※5)メーカーにおいて、先頃量販店チャネルで自社の中核商品にチャネル側の管理不全によって不良品が発生する事故が起きました。
この事態をいかに解決すべきかという課題に対する結論を導き出すために、結論の下にMECEの関係にある4つの要素(根拠)を並べました。
論理パターンを理解する② 解説型
論理の基本パターンには実はもうひとつあります。
ここでは解説型について説明します。
解説型では結論を頂点にその下の階層に並列型の同じように複数の根拠が並んでいます。
上下の要素が So What? / Why So?(結局どういうことなのか? / なぜそのようなことが言えるのか?)の関係で階層化されているのは並列型と同じです。
並列型との違いは解説型の根拠が「事実」と、「判断基準」「判断内容」の2つに別れている点です。
「事実」は課題に対する結論を導き出すために、相手と共有しておくべきもの。
また、「判断基準」は「事実」から結論を導き出すための伝え手としての判断。
最後に「判断内容」は「事実」を「判断基準」で判断した結果、どのように評価されるのかというもの。
前章で紹介した消費財メーカーにおける不良品への対策も解説型によってより良い結論を導き出せます。
コラム:ロジカルシンキングのデメリット
ビジネスシーンにおける商談や会議などの場面で論理的に自分の考えを説明することができ、相手に納得・共感してもらうためにとても有効なスキルであるロジカルシンキング。
しかし、そのようなロジカルシンキングにも欠点はあります。
たとえば、ロジカルシンキングは相手を説得するときなどに大変有効なツールですが、そこで得られた結果がすべて正しいとは限りません。
そして、正しいと信じ込み強引に進めようとすると、思わぬトラブルを生じさせる原因になることがあるのです。
また、自分では論理的に明確に説明できて自信があっても、そのような考え方に拒絶反応を示す人もいます。
したがって、話を円滑に進めるためには相手の反応を確認しながら進める必要もあります。
ロジカルシンキングは決して万能ではありません。
全く新しい未知の分野においては論理を組み立てる要素が少なく、ロジカルシンキングのツールを使うことが困難な場合もあります。
このようなデメリットもあることを理解して、ロジカルシンキングを活用しましょう。
▼▼▼こちらもおすすめ!▼▼▼