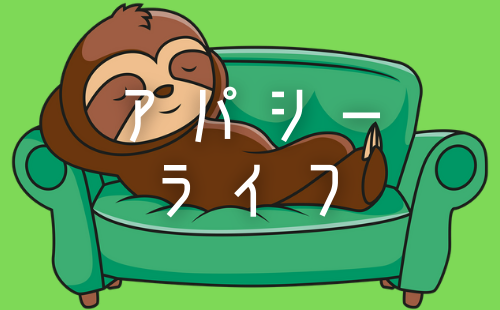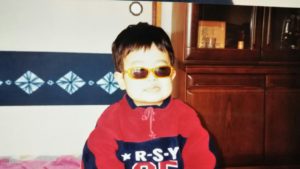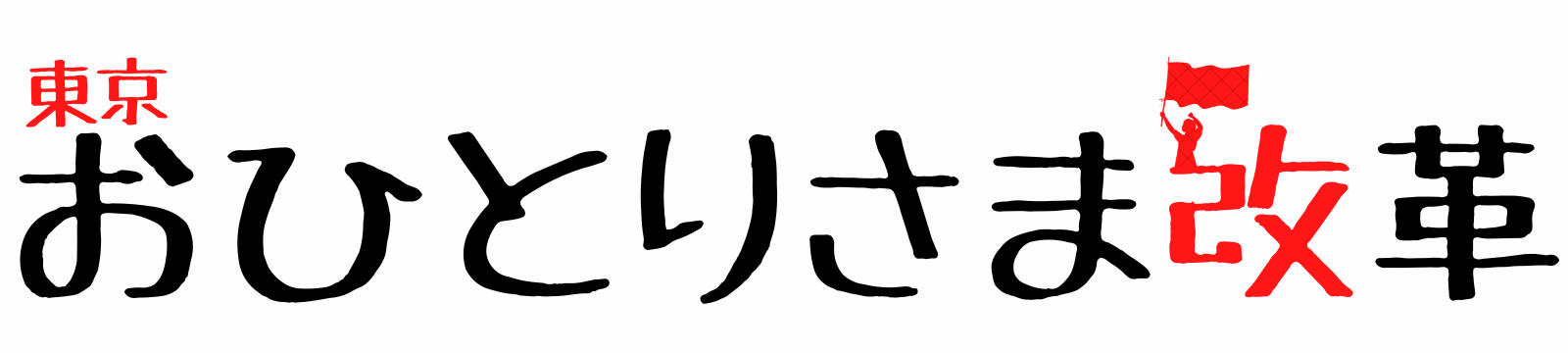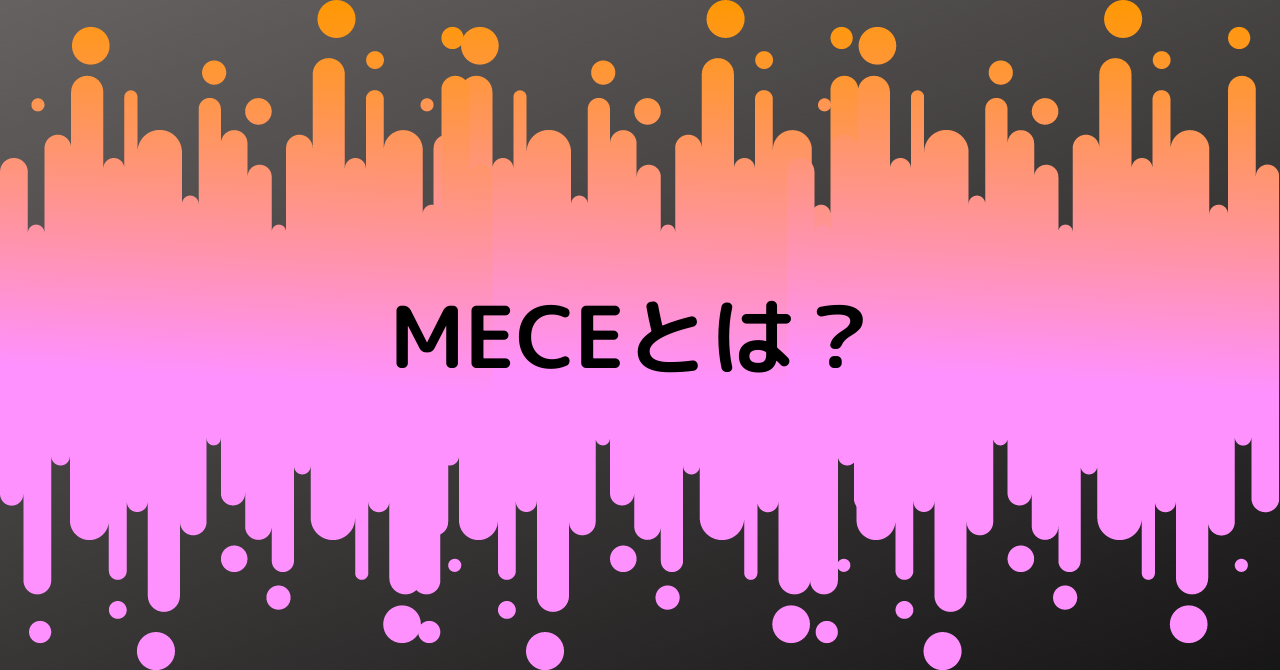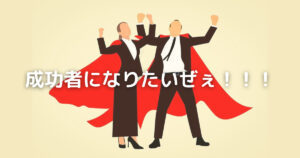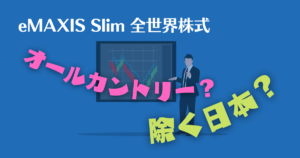物事を分解して考えるときに大切になるのが「MECE(モレなくダブりなく)」。
検討にモレがあったり、重なりがあったりすると正しい結論に行き着くことはできないでしょう。
「MECE」とは
漠然とした項目設定は要素のダブりを生み、大事な要素を見落とすことにもつながる。
そうならないよう全体を俯瞰しましょう。
MECE(ミーシー)とは、Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive の略で、モレなくダブりなく、という意味です。
新しい企画や対策などを考案するときには、対象となる市場を俯瞰して、その構造や需要などを的確に把握しておく必要があります。
しかし全体を漫然と眺めていたり、整理項目を思いつくままに並べていくだけだと、並べた項目に要素のダブりがあったり、思わぬ要素がぽっかりと抜け落ちていたりします。
これでは、そのあとの論理の構築も穴だらけになりかねません。
対象を構成する要素にどんなものが含まれるか、ダブりやモレがないよう常に意識しながら進めることで、ピラミッド構造を構築する際に必要な項目を整理できるようになり、項目の追加や削除などが可能となってきます。
物事の範囲を可能な限り大きく捉える
核となる守備範囲とそれ以外の要素も常に検討範囲に加えることで、ビジネスの多角化(※1)やシェアの拡大に結びつけましょう。
企業内で主軸としているサービスが好調だったとしても、現行の業務に関連した新企画を展開するだけでは、サービスの密度こそ濃くなるものの、市場の拡大や多角展開には結びつきません。
また、環境の変化に柔軟に対応できなくなるというデメリットもあります。
事業に発展性を持たせるためには、既存の守備範囲の外にも常に注意を払っておく必要があるのです。
たとえば子ども向けのオモチャやプラモデルを売る会社の場合、子どもだけを顧客と考えていたら市場はそれ以上成長しません。
しかし大人やシニアにも受け入れられる商品を開発していけば、市場規模は一気に拡大します。
また、海外にまで市場を展開させることも可能となり、逆に海外から国内市場に進出してくる強豪メーカーにシェアを奪われるリスクも軽減されます。
考える要素にモレやヌケがあると的外れな思考に陥る
一方的な都合や判断基準は考える要素のヌケやモレを生む。
ビッグピクチャーを展開して、さまざまな要素を検討しましょう。
多機能な商品を開発することは大切ですが、それが「売れる商品」とは限りません。
なぜなら、「多機能だから売れるだろう」というのは作り手の側の一方的で的外れな思い込みにすぎず、そこには「消費者がなにを求めているのか」という視点が抜け落ちているからです。
事業計画には、常に「前後・左右・上下」へと多面的にビッグピクチャーを描いて考える必要があるのです。
新しい人材Aさんを採用するシーンで考えてみましょう。
最初はどうしても学歴や個人の能力が判断基準になります。
しかしそれ以外にも、社内で上司や同僚、部下と良好かつ創造的な人間関係が構築できるか、どのような顧客を獲得できるか、他社に採用された場合の損失はどれくらいか、採用されることがAさんにとってプラスなのかどうかなど、考慮すべき材料は無数にあるのです。
ビジネスマン必須のMECEのフレームワーク1 3C分析
経営戦略や計画の現状分析を行うための代表的な分析手法である3C分析とSWOT分析について見ていきます。
3Cとは、「Customer(市場・顧客)、Competitor(競合)、Company(自社)」の3つの頭文字を取ったもので、マーケティング環境をヌケやモレなく把握するためのフレームワークです。
マーケティングの本質は、いくつも存在する施策の中から最も効率的なやり方に資源を集中投下し、顧客に選ばれ続け売上や目的を達成できる仕組みを作り上げること。
3C分析はその心強い味方です。
3Cの一角を占める「自社」の現状を分析するのに役に立つフレームワークがSWOT分析(※2)です。
「強み(Strength)」は技術力の高さなど、自社が持つ強みを指します。
「弱み(Weakness)」は自社が苦手にしている部分、「機会(Opportunity)」は自社にとってビジネスチャンスとなるような環境変化などの外部要因、「脅威(Threat)」は自社の強みを打ち消してしまう危険性のある環境の変化や、競合他社の動きなどを指します。
ビジネスマン必須のMECEのフレームワーク2 PPM
複数の事業を行っている企業が、事業資金をどう配分するかを決める際に使うフレームワークがPPM。
効果的な投資方法が見えてきます。
PPMはプロダクト・ポートフォリオ(※3)・マネジメントの略称。
経営資源(※4)を最適に配分することを目的として、ボストン・コンサルティング・グループ(※5)が1970年代に提唱したマネジメント手法です。
企業の展開する複数の製品・事業の組み合わせと位置づけを分析し、全社レベルで最適な経営資源配分を判断するためのフレームワークです。
企業が展開する複数の製品・事業を、(1)問題児(育成すべき段階)、(2)花形(現在の取り組みを維持・継続する段階)、(3)金のなる木(投資を抑えて収益を回収・収穫する段階)、(4)負け犬(撤退する段階)の4つに分類して、事業戦略の検討に役立てます。
金のなる木で得た利益を市場成長率の高い問題児に投入し、花形に育成するのが基本戦略です。
ビジネスマン必須のMECEのフレームワーク3 バリューチェーン
企業活動の各段階で、どれだけの価値を生み出しているかを分析するのがバリューチェーンというフレームワークです。
バリューチェーンとは、事業活動を機能別に分類し、どの部分においてどのくらいの量の付加価値が生まれているのかを分析することによって、競合と比較してどの部分に強み・弱みがあるかを分析し、事業戦略の有効性や改善の方向を探ることを目的としたフレームワークです。
すなわち、原材料や部品の調達活動、商品製造や商品加工、出荷配送、マーケティング、顧客への販売、アフターサービスまでの一連の事業活動を、個々の工程の集合体ではなく価値(Value)の連鎖(Chain)として捉える考え方です。
自社に対するバリューチェーン分析の実施により各プロセス内で発生している付加価値の量やバランスを把握することで、ライバル企業よりも優れている点や劣っている点を明確にすることができます。
ビジネスマン必須のMECEのフレームワーク4 問題発見の4P
企業が抱える問題を発見するためのフレームワークのひとつが「問題発見の4P」。
これにより問題の輪郭が明確になっていきます。
「問題発見の4P」とは問題を発見・理解する上で決定すべき、「Purpose(目的)」、「Position(立場)」、「Perspective(空間)」、「Period(時間)」の4つの要素のことを指します。
「Purpose」は目的を明らかにすることです。
「Position」は誰にとっての問題かをはっきりさせることです。
「Perspective」は思考が十分に広がっているかどうかというチェックポイントです。
最後の「Period」はどの時点での問題かを明らかにすることです。
たとえば、社長の問題意識を考えてみましょう。
もしかしたら、企業をダメにしてしまう社長は、売上目標の達成が目的で、立場は自分が中心、視野の広がりは目の前の顧客、時間軸は自分の任期といった具合になっていないでしょうか。
このような社長が経営する会社はいずれ市場で淘汰されるでしょう。
時間軸と空間軸の2つで全体像を理解する
時間的・空間的な広がりの中でマーケット・ライフサイクルを把握することで今後の展開を的確に予想することができます。
あらゆる現象は、横軸を時間、縦軸を空間とした図表で表現することができます。
ビジネスの世界でもこの概念はよく用いられ、たとえばある事業の推移を「導入期」「成長期」「成熟期」「衰退期」という4つのライフサイクルに分けることが可能です。
世界的なムーブメントを起こしている何かがあるなら、4つのサイクルのどの段階に達しているのかを見極めることが大切です。
これがまだ導入期や成長期であるとしたら、これから設備投資をして大きな利益が得られるかもしれません。
しかし、すでに成長期や衰退期に入っているとしたら、次のムーブメントを見据え、新しい企画を仕掛けていくほうが効果的です。
これはリスク管理の観点からも有効で、たとえば世界的な金融危機が発生したときのケースを分析し、どの段階でどんな対策が有効かを見極めることも可能になってきます。
手順を圧縮して効率を上げる
目的がはっきりしていれば手順を圧縮して簡略化でき、新しい課題に進んでレベルアップできます。
自社の業績が思わしくないとき、問題点や解決策を多角的に分析していくことには大きな意味があります。
しかし、分析の段階で何を目的としているのかがはっきりしていないと、次々と出てくる分析データや解決策も焦点が定まらず、無駄な手順が多くなってしまいます。
まずは最初のステップにシンプルな目的を設定し、それを実現するための最短コースを探る必要があるのです。
たとえば受験勉強で数学の公式を勉強しているとしましょう。
公式をノートに書き留めてまとめ、それから公式を覚え、それからようやく練習問題を解いていたのでは、時間の無駄です。
公式を使えるようになりたいという目的さえはっきりしていれば、練習問題を解くまでの過程を圧縮できるでしょう。
そこで時間の余裕ができれば、さらに高度な問題を解いてレベルアップできるのです。
MECEを活かした情報処理(グルーピング)を行おう
どのように項目を整理していくか悩ましいときは、要素をグルーピングしていくボトムアップ式の構築が有効です。
ひとつの課題をピラミッド構造で分析していこうとすると、多くの人が「どうグループ分けしていったらいいかわからない」という問題に直面します。
こういうときは、思いつくままに具体的な問題点をいくつも書き出していき、それを一定の共通項目ごとにグルーピングしていくと、出発点まで遡ることができるようになります。
このボトムアップ式の整理法は、発案者である川喜田二郎氏の名に因んでKJ法と呼ばれています。
商品の売上が伸び悩んでいる理由を分析したくていくつかの要素を列挙した場合、それを「商品に関するもの」「価格に関するもの」「チャネルに関するもの」「プロモーションに関するもの」などの大枠でまとめていけば、問題を構成する要素が見えてきて、解決策を検討する方向性もはっきりするのです。
コラム:NSチャートで、モレのない思考法ができる
コンピュータのプログラミング方法にNSチャートがあります。
NSチャートはフローチャートとほぼ同様の論理的思考法です。
ただフローチャートと違い、四角形の枠組みの中だけで考えるため、モレ(バグ)が出にくく、より効率的に論理的思考ができるものです。
例を挙げましょう。
あなたは上司に企画案を提出します。
これをNSチャートで考えます。
まず企画が通るか。
ここでYESならば、そのまま企画を進めればいいだけ。
しかしNOならば、なぜダメなのか理由を問います。
アイデア自体がダメなのか訊いたとします。
ここでYESならば代替企画の用意が必要です。
NOならばさらに訊きます。
コストが問題でしょうか。
ここでYESならば企画の主旨を変えずにコストだけを削減する予備案が必要になります。
それでもNOで、ほかに思い当たる理由がなければ、その要因をヒアリングするという結論になります。
このような思考図を作ることで、前もって相手の答えに対する、より的確な対策を取ることができるのです。
なおNSチャートは、質問が多くなりすぎて1つの図に書き切れなくなった時に、メインの図(ルーチン:RTN)のほかに、サブの図を作り、適宜サブに飛ぶようにすれば、コンパクトに作れます。
▼こちらもおすすめ!▼