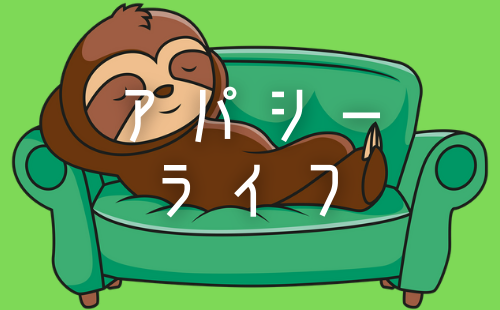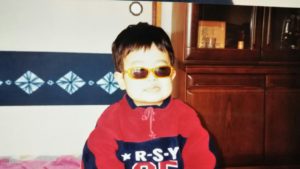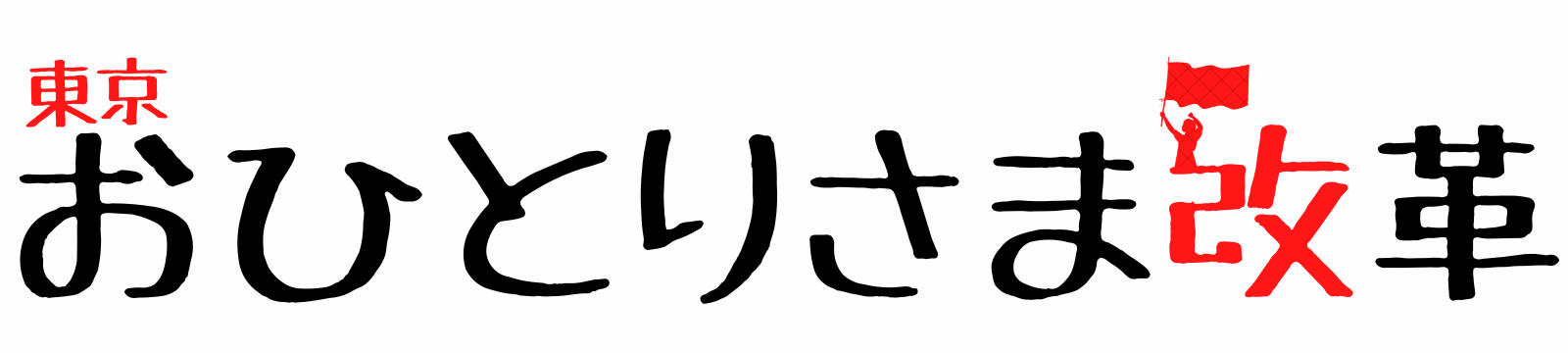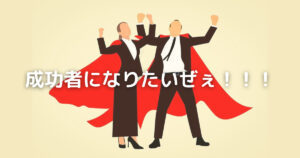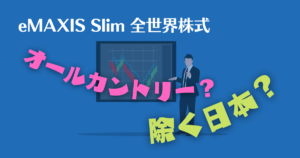相手を説得して自分の望む方向に誘導するのにはかなりの経験が必要。
しかし、ロジカルシンキングを用いたコミュニケーション術を使えば、簡単に相手を共感・納得させることができます。
結論から先に述べる

相手が一番知りたがっているのは「結論」です。
最初に結論を述べることで、ロジカルに理由を説明することが可能となり、聞き手にしっかり伝わるのです。
自分の中にある考えを正確に聞き手に伝えることが「ロジカル・コミュニケーション」の基本です。
ロジカル・コミュニケーションは、結論を述べたのち、その理由や根拠を示します。
それが、結論から始める「アンサーファースト」です。
例を挙げてみましょう。
「我が社はアジア地域へ進出するべきです(結論)。アジアでの△△のニーズが高まっており・・・(理由)。提携会社B社の現地での業績は堅調で・・・(事実)」。
結論から理由、事実までわかりやすい流れができているでしょう。
アンサーファーストは、最初に結論や仮説を述べます。
相手が最も知りたいのが結論ですから、話のスタートから大きなインパクトを与えることができます。
また、聞き手側も、最初から話のテーマを絞り込むことができるので、理解がより深まります。
日本の場合は、結論を最後に持ってくる論法が一般的です。
日本語の文法に由来する特性とも考えられますが、だからこそアンサーファーストを常に心がけることで、他者に先んじたより洗練したスピーチが可能になるといえます。
「結論」→「根拠」→「たとえば」の3段ピラミッドで話す
説得力のある話し方の基本は、結論を述べたあとに根拠を説明して「たとえば」とつなげて実例を挙げること。
このピラミッド構造の作成を常時心がけましょう。
論理のピラミッドは、結論→根拠→事実の3段構造で作るとより具体的でわかりやすくなります。
まず結論が頂点に位置します。
もちろん、ひとつだけです。
続いて根拠(理由)が2段目にきます。
これは3つのポイントに絞りましょう。
最後が事実(裏付け)です。
これは場合にもよりますが、1つの根拠に対して1つか2つでいいでしょう。
また、冒頭に「たとえば」とつけて実例を挙げると、より説得力が増します。
これでピラミッド・ストラクチャーが完成しました。
次に、ピラミッドの作り方について説明します。
まず、必ず結論から作る必要はありません。
自分で作りやすい順番に組み立ててください。
ひと通り組み立てたら、ピラミッドのすべての線で「○○だから」「○○である」と読んでみて、意味が通じるかどうか確認します。
通じなければ、中身を入れ替えていきます。
根拠と事実を入れ替えてみるなど、いろいろ試してみましょう。
常に論理をピラミッドに構築することを心がけていれば、ロジカルシンキングが身につきます。
ポイントを3つに絞る
話す内容を3つにまとめることで、聞き手は内容の全体像をイメージすることが容易になり、また、話す側も論点を絞り込んで整理できるようになります。
結論を述べたあと、その根拠を話す際に、ポイントを3つに絞ると、相手に伝わりやすくなります。
「3つ」という数字を示すことで全体像がわかるので、聞き手もまた、3つの根拠を頭の中で組み立てて理解を示そうと用意してくれますし、話の内容を整理することも容易になります。
どれだけの量を話すのかイメージができなければ、聞き手の負担が増してしまうことにもつながり、理解度が下がる恐れもあります。
聞き手を安心させて理解を深める効果的な方法なのです。
この方法は、聞き手だけではなく、話す側にも大きな利点があります。
内容を3つに絞ることで、ロジカルに整理して伝えることになりますから、説得力が高まります。
また、話の論点を十分にまとめていなかったり、事前の打ち合わせでしっかり考えていなかった場合にも、強引にポイントを3つに絞り込んでしまうことで、自然と論点を整理することができます。
「ポイントは3つ」と宣言することで、聞き手と同じく自分自身も話をまとめていくことができるわけです。
CRFの原則を使えば、話に説得力が増す
ピラミッド構造を活かした説明方法がCRFの原則です。
C(結論)、R(根拠・理由)、F(事実・裏付け)の順番で話すことで、説得力が増すのです。
説得力を飛躍的に高める方法に、3段階のピラミッド構造で構築されている「CRFの原則」があります。
Cとは Conclusion で結論、Rは Reasons で理由・根拠、Fは Facts で事実・裏付けを表します。
まず、アンサーファーストで結論を頂点に置きます。
次に理由や根拠を3つのポイントに分けてピラミッドの2段目に置きます。
最後に事実・裏付けをそれぞれの理由・根拠に1つ〜2つ付与して、3段目に配置します。
これでピラミッド構造が完成し、自分の伝えたいことをロジカルに話せるようになります。
CRFの原則をわかりやすく説明しましょう。
C=◯△という商品には将来性がある。
R=①デザインの評判がいい。②コストパフォーマンスがいい。③海外ニーズが見込める。
F=①について。ネット上での評価。新鋭デザイナーの起用。②について。既存商品のパーツを一部流用可能。原材料の安価購入ルートの確率。③について。海外同業他社の実績。
以上のように、それぞれの要因についての検証がわかりやすいので相手の理解度が上がるのです。
パワーポイントを有効に使う
言葉だけで説明する以外に、パワーポイントを活用して視覚に訴える方法があります。
表や図などを見せながら話すことで、より大きな効果が期待できます。
パワーポイントというソフトがあります。
プレゼンでは視覚情報が重視されることは知られていますので、パワーポイントの活用は、現代では必須事項といえるでしょう。
基本的な使い方は、1枚のスライドにメッセージと1つ〜3つの図表、コメントで構成します。
1枚のスライドの中に完結した全体像があることを相手に分からせるのが目的です。
スピーチを裏付けるビジュアル面での情報は、聞き手の理解度を大きく向上させますから、活用方法を覚えておきましょう。
パワーポイントで伝えたいメッセージに合った分析や事実を伝えるのに必要なのは、絵のセンスではありません。
むしろ、論理の力がものを言います。
メッセージと論理構成が明確なら、表現するべき内容が「比較」なのか「構成比」なのか「バラツキ」や「変化」なのか、それぞれの違いに合わせて構成を変えられます。
プレゼンテーションでは、スライドの完成度で聞き手とのコミュニケーションの効果に大きな差が出てしまいます。
時間を多めに使ってでも有効に活用してください。
一次情報、定量情報、中立情報の3つを重視する
論文や記事などの二次情報より「生」の情報である一次情報が大切。
さらにデータに基づく定量情報、客観的な中立情報が加わればより強力です。
論文や記事などの二次情報を鵜呑みにしていると、事実関係と異なる状況が生じて、混乱することがあります。
それは二次情報が、発信元によって断片的に流されている情報だからです。
「□○という車はいい」という記事を見て車を購入した人が、故障が多くて不満に感じた場合、記事を書いた人は昔の車と比較して「いい」と評価していたのかもしれません。
では、□○の車を試乗してから決めたらどうでしょう。
これは自分自身で集めた「生」の情報である一次情報になります。
一次情報の活用は、ビジネスマンにとって必須といえます。
二次情報では伝わらなかった現場の問題点を、目や耳、肌で感じ取ることで発見し、より良い状況へと発展させることも可能となります。
次に大切なのは定量情報です。
これは具体的な数値に基づいた情報です。
車なら「燃費がリッター20kmに上がった」の方が「燃費が良くなった」よりも説得力があります。
中立情報も重要です。
顧客や第三者からの直接的な意見や評価はバイアスがかからない分、貴重な判断材料となります。
ピラミッド構造に物語性を与えて人の心を動かす
「CRFの原則」「アンサーファースト」はピラミッド構造の基本ですが、それを物語として構成することで強い共感を生み出し、より深く理解させることができます。
「CRFの原則」による説得力、「アンサーファースト」が生み出すインパクトによって構築されてきたピラミッド構造をさらに1段階高める手法があります。
それが論理を物語として構築していくことです。
ピンと来ないかもしれませんが、伝えたい内容をひとつの物語として語りかけることで、ストーリー展開に集中させて、なおかつ共感を生み出すという効果が期待できます。
論理を理解してもらうことも大切ですが、共感という感情的な部分で繋がることも有効なのです。
物語にするといっても、難しく考える必要はありません。
まず、伝えたいことをすべて書き出してみます。
ピラミッド構造のCRFを、箇条書きのような形でもいいから何もかも文章にします。
次にそれらの文章でひとつの流れを作ります。
この場合、アンサーファーストにこだわる必要はありません。
より効果が出ると思えば、結論を最後に持っていっても構いません。
大切なのは、「一筆書きのストーリー」として、伝えるべきことを残らず聞いてもらうことなのですから。
話す前の2つの確認①
課題(テーマ)を確認する
スピーチの前や文章を書く前に、必ず「今日話すテーマ」について確認してみましょう。
論点がずれてしまっていては、相手には何ひとつ伝わらないからです。
CRFの原則を活用してすばらしい理論のピラミッド構造を考えたとしても、スタートにつく前の段階に落とし穴があるケースをよく見かけます。
課題を検証していくうちに、その根拠や事実に別の要因があると、本来進めるべきだった課題から離れて、その別の要因の問題追及に重点を置いてしまう場合です。
そして、結論に至る問題の解決こそ急務だと考えてしまい、自分の中で本来のテーマより優先度が上がり、結果として会議の場で論点のずれたスピーチをしてしまうのです。
スピーチとは聞き手に自分の伝えたいことを理解してもらうために行うものです。
課題の検証の段階で、問題点を発見したとしても、そのテーマから逸脱してしまったのでは、聞き手の混乱を招くだけです。
「①課題の検証→②問題点の発見→③解決方法を解析→④解決方法の提案」という流れのどこに問題があるかわかると思います。
③と④は本来の課題と分けて考え、別の機会で議論するべきです。
自分の中だけで自己完結してしまう「自分のことしか見えない病」に注意してください。
話す前の2つの確認②
相手に期待する反応を確認する
理解しやすいスピーチと同様に大切なのが、相手にどのような反応をしてもらいたいのかを決めておくこと。
期待する反応次第でスピーチの内容も変わります。
スピーチの目的は、自分の考えを一方的に聞いてもらうことではありません。
課題を掘り下げて、根拠や理由を検証し、事実や裏付けをそろえたのは、自分の話したテーマを聞き手に理解してもらうとともに、それに対するリアクションを期待しているからです。
さらに一歩踏み込んで考えれば、自分が期待する反応を引き出すための工夫をスピーチの方法論に組み込むことで、より大きな効果を得ることができるわけです。
相手に自分が期待する反応を引き出すのがスピーチの最終目的ともいえます。
相手から引き出したい反応も様々です。
賛同を得たいのか、相手のニーズ(※1)を知りたいのか、アドバイスを聞きたいのかでスピーチの内容も変わっていきます。
ケースによっては、スピーチを3段階に分けて、それぞれ期待するべき反応を変える場合もあります。
例えば、ある提案をしたい場合、第1段階では提案することの許可を得て、第2段階で提案についてのアドバイスを引き出し、最終段階で提案を認めてもらいます。
期待している反応に応じて話の内容を変えていくことも大切なのです。
結論が伝わらないときの2つの落とし穴①
自分が導き出した結論が、相手が求めている結論と食い違ってしまうことがあります。
結論とは課題の要約であり、自分の言いたいことの要約ではないのです。
課題について考えるうちに、様々な理由や根拠が並列してしまうことがあります。
それぞれの理由や根拠には事実や裏付けがなされており、一見強固なピラミッド構造に見えますが、それらの理由・根拠をまとめていくうちに分析結果そのものが結論にすり替わり、相手が自分に求めている解答と食い違ってしまうのです。
「AかBか」と聞かれたのに、「Aも悪くないがBも捨てがたい」では回答になっていません。
聞き手は「Aです」、または「Bです」が聞きたいのですから。
なぜ食い違いが生じるのでしょうか?
「AかBか」という課題に従って検証を進めていくうちに、「Aにはこういう部分が」「Bには隠れた実績が」といった事実に基づく情報が加わり、それが根拠となって「Aは悪くない」「Bも捨てがたい」という結論にすり替わっていくからです。
しかし、そこからさらに深く分析して「A(B)である。なぜなら・・・」という解答を導き出さなければ相手は納得しません。
常に課題と向き合うことが食い違いを起こさない最善策なのです。
結論が伝わらないときの2つの落とし穴②
結論を明快に述べても、どちらとも取れる付帯条件をつけることで、効果が激減することがあります。
曖昧な条件付けより具体的な実施基準を示しましょう。
スピーチで結論を述べたのに、曖昧な付帯条件をつけたために台無しになることがあります。
精査したCRFのピラミッド構造の理論で相手に理解させたとしても、それは同じことです。
その原因は「具体性のない曖昧な条件」によって異なった解決方法の選択肢が生まれてしまうからです。
例えば「A国に投資する」という結論が出たとします。
そこに付帯条件で「状況によってはA国に限らない」となると、為替(※2)の変動あるいは国際紛争が条件なのか、またA国以外なら投資をやめるのかも不明です。
曖昧な付帯条件のリスクは、実行者の勝手な判断に課題の実現方法を委ねてしまうことです。
課題を勝手に解釈して企業やクライアントの意図に反する行動に走るかもしれません。
また、逆に実行者はできないこと、やらなくていいことの言い訳として利用するかもしれません。
もし付帯条件をつけるのであれば、テーマの本質に基づいたものにする必要があります。
「状況」ではなく「国際紛争」、「A国に限らない」を「その場合はB国」とすれば、課題を補う具体的な条件となります。
根拠が伝わらないときの3つの落とし穴①
結論だけを強調して、そこに至った理由も事実関係も重視しないで話をする人がいます。
アンサーファーストもCRFの原則を活かさなければ効果はありません。
トークにインパクトを与えるアンサーファーストを実行しても、そのあとにCRFの原則を活かさなければ、意味がありません。
話し手が陥りやすい間違いの1つが、結論だけを主張して、理由と事実を分析しないケースです。
たとえ結論と課題が整合していても、それを支えるピラミッド構造の論拠がなければ、相手の理解は得られません。
結論はそこに至る理由や根拠によって支えられています。
そして根拠は事実の裏付けが支えています。
そのロジックを間違えてはいけません。
悪い例として「①A社と提携したい②A社は我が社にないテクノロジーがある」という提案です。
①はともかく②は「A社の意向は?」「テクノロジーがなぜ必要か?」「費用対効果の見積もりは?」という疑問を生じさせて、「A社は前向き」「会社の将来性に欠かせない」「1年以内に収益黒字の予想」など、それぞれに事実の裏付けを行い、初めて提案として検討に値するかどうか判断するという段階に至ります。
最初の提案では、聞き手は何ひとつ判断材料がなく、ただ困惑するだけでしょう。
根拠が伝わらないときの3つの落とし穴②
F=裏付けの事実こそがCとRの信憑性を高める論拠です。
しかし、その論拠が曖昧なものとして受け止められてしまえば努力が水の泡になってしまいます。
どんなに完璧なピラミッド構造を構築しても、その根底を支えている事実や裏付けに曖昧な部分があると、理由や結論までが脆弱で説得力のないものになってしまいます。
そうならないためには、事実の裏付けが客観的な事実なのか、自分の判断に基づいたものなのかを区別しなければなりません。
客観的事実は数値化されたデータなどです。
一方、自分の判断や仮説も、そこへたどり着くまでの筋道や発見点などを明確に答えることができれば、裏付けや事実として理由を支える役割を担えます。
一番の問題は、それが客観的な事実なのか、自分の判断なのかを曖昧にしてしまうケースです。
聞き手からすれば、そこがはっきりしない限り、理由や結論も信憑性は低いと考えざるを得ません。
客観的事実なら数値などのデータを示すべきですし、自分の判断ならそこへ至った説明が求められます。
そこを曖昧にしていては「事実や裏付けがない→根拠や理由が薄弱→結論も疑わしい」と判断されます。
客観的事実か自分の判断かを明白にして、その傍証を用意しておくことが必要です。
根拠が伝わらないときの3つの落とし穴③
課題についての前提条件や判断基準を、自分の思い込みで決めてしまう人がいます。
課題の答えは、事実をどう見るかという判断の軸によって決まるのです。
前提条件は、なぜその課題に取りかからなければならないのかの基軸といえます。
それが決まってからCRFのピラミッド構造理論が構築されます。
いわば、ピラミッドを建てる上での土地のようなものでしょう。
「Aを大々的に売り出す」という課題が上がった場合、Aを売り出す理由やそれを支える事実と同時に、売るという前提はどうして決まったのかを問われます。
話し手が「そんなことは当たり前」と思っていたとしたら、課題の説明以前の段階で相手を混乱させてしまいます。
判断基準についても、同じように自分だけの思い込みで決めてしまうことがあります。
判断基準とは、その課題について「この場合はこうする」「こうなったらこうする」といった様々なケースに対応するための決まり事です。
これがブレると、トラブルの発生や事業の拡大、あるいは撤退などの問題が発生した際に足並みが乱れてしまう恐れがあります。
前提条件をしっかり伝えた上で課題を説明すること、また、判断基準を明確に示すことで、思い込みによる混乱をクリアできるのです。
方法が伝わらない2つの落とし穴①
10年前でも10年後でも通用するような戦略は、単なる定義にすぎません。
自分の会社の状況に即した具体的な方法を考えなければ、相手に伝わっていきません。
企業の戦略とは、その時代や状況に合わせてフレキシブル(※3)に変化していかなくてはなりません。
会議で会社の今後の指針について議論するとき、10年前でも10年後でも通用するような、抽象的な発言をする人がいます。
それでは、教科書に書いてあることをそのまま覚えて、口に出しているようなものです。
10年前にも通用していたということは、それは定義となっているにすぎません。
他の会社でも同じように通用している公理ですから、もはや自分の考えとは言えないのです。
戦略を述べるには、全てをロジカルに考えて、具体的に話を組み立てていけばいいのです。
これは会議だけではありません。
日常的な業務の中でも、具体的な指示や要望を出さない上司やクライアントと仕事をしなければならないケースはあります。
そんな場合、相手の考えを頭の中で推し量っているだけではいけません。
そんなときは「それはこういう意味でしょうか」などと質問や確認をしましょう。
物事を具体的に伝えるのは、話し手と聞き手の共同作業であり、共同責任なのです。
方法が伝わらない2つの落とし穴②
修飾語を増やして内容を水増ししても、何ひとつ解決しません。
どうしてそうなったのかという原因を遡って検証していけば具体的な問題解決へ至るのです。
取り組んでいる問題の本質が理解できていない場合、多くの人が修飾語で中身を膨らませ、ごまかしたい誘惑に駆られます。
しかし、どのように言葉を飾ったところで、内容が良くなることはありません。
問題自体が解けていないのですから、具体的な説明をすることには無理があります。
そういうときは、まず、自分がどこまで理解していて、どこから理解できなくなったのか、遡って検証してみましょう。
書き方や組み立て方の前に、まず考え方のチェックを行うのです。
まず、今わかっていることについて「なぜそうなっているのだろう」「どうしてそういうことが起きたのだろう」と自分自身に問いかけてみます。
それらを具体的に書き出し、話していくことで、「どうすればよいか」が具体的に考えられるようになります。
なぜなら、書き出すことや話すことができるということは、そこまでの問題が解けていると言えるからです。
また、相手の気持ちになって「何を知っていれば具体的に動けるか」をイメージしてみるのも有効な方法です。
話の重複は自分の頭が混乱中であるサイン
複数の理由について説明する際、内容が重複してしまう場合があります。
説明自体に混乱が見えるようでは、結論に対する信憑性も大きく損なわれてしまいます。
スピーチで論点を3つの根拠に絞り込む方法はとても効果的ですが、中には3点のうち内容が重複しているケースが見受けられます。
全く同じことを言う人はいないでしょうが、一見切り口は違っていても、言わんとしていることが重なる場合は多々あります。
これらを防止するには、話す前に課題を具体的に整理して、客観的なデータや数字を出すなど、それぞれの根拠の差別化を図ることで、類似した論点でも個々に論じている内容の違いが出てきます。
話の重複について対策を考えるのは、話し手だけではありません。
むしろ、聞き手側の手腕が問われます。
まず、もっともらしい話の中から重複しているポイントを聞き分けることです。
話し手自身がしっかり分類できていると思い込んでしまったスピーチですから、そのまま気づかずにスルーしてしまう危険性もあります。
話の内容を分析して重複していると認識したら、話し手に、重複箇所について具体的な質問を投げかけてみれば、相手も自分の間違いに気づくでしょう。
話のモレは会話の信頼性を一気に崩壊させる
課題そのものに、重要なモレがある場合もあります。
いくらCRFをしっかり構築しても、自分の知らない問題点を内包したまま話を進めていては信用されません。
CRFの原則でしっかりした理論を構築して会議に臨んでも、とんでもないミスを犯す危険性があります。
それは、課題そのものについての自分自身の知識不足です。
「この商品は売れる。それはこういう根拠だからだ」と述べても、原料の××に輸入規制がかかったことを知らず、それを指摘されたらどうでしょう。
もし、会議に出ている人たちには周知の事実で知らないのがあなただけとしたら、いつ原料が途絶えるかわからない商品の話を誰も真剣に聞いてはくれないでしょう。
これは基本的な話の「モレ」です。
課題を構築する上で、知っておくべきことが漏れてしまうというイージーミスですが、ビジネスの世界では信用を失うということは大きな痛手です。
これは、基本に立ち返って、常に課題と向き合い、その課題についての情報や風評に耳を傾け、場合によっては現地調査も行って、段取りを十分につけておくことでミスを防ぐのが唯一の方法です。
企画の推進に夢中になって、調査や情報収集をおろそかにしないことを心がけていくしかありません。
話のズレがそもそもの目的やテーマからの脱線を招く
会議を進めていく中、全く関係ないはずのRやFが提案されることでズレが発生して、本来の課題やテーマから脱線してしまうケースがあります。
会議におけるスピーチで、時折、本論からズレたことを話す人がいます。
課題=結論がはっきりしているにもかかわらず、本人は整合性があると信じて、自信を持って話し続けます。
聞き手の誰かがズレに気がついて否定すれば単なる時間の無駄で済みますが、RやFがそれなりに構築されていると、すんなりと内容を受け入れられて、議題の本筋から脱線する羽目になります。
そして、そのまま走り続けて全く関係ない結論へ至ってしまうこともあるのです。
1例を挙げます。
「AとBどちらの会社に出資するか」という会議で、「実はCが新技術を開発したという情報がある」と誰かが発言します。
聞き手たちは「Cも検討しよう」と課題自体を変えてしまいました。
もちろん、AとBのどちらかに決めるという課題とCの検討という提案は別に考えるべき問題ですが、Cも魅力的だという考えが脱線を正当化したのです。
「それは別問題なのでCについては改めて議題に上げよう」と軌道修正する意見が出ていれば、話は本来の場所へ戻れたわけです。
話が急に飛んだりすると、相手を疑心暗鬼にさせる
課題を進めていく上で一番困惑するのが話の「飛び」です。
根拠や理由を述べているのに、全く脈絡のない結論に到達したら対応の方法がありません。
構築されたCRFのピラミッド構造で会議が進行していても、途中で明らかな違和感に襲われることがあります。
主な原因は話の「飛び」です。
精緻に構築されたCRFであるはずなのに、事実がその会社が内包する事情や願望とすり替わっていたり、根拠が現実とかけ離れたものに変わっていたりすることがあります。
「飛び」が発生するのは、主に結論に対して不確定な要素が干渉した場合です。
「飛び」は間違った結論へ至るリスクが最も高く、企業にとって重要な問題です。
ある会社が業績不振を理由に営業社員を新規顧客開拓に回し、既存の顧客は外注スタッフに任せたとします。
さらに成績不振の社員はリストラすると通告します。
しかし、顧客は外注スタッフの対応を嫌がり、元担当に連絡します。
結果、社員は顧客の対応をせざるを得なくなり新規獲得はできずにリストラに。
会社は人材不足という結果に。
顧客と営業マンの信頼という「事実」が、新規開拓で業績向上という会社の「願望」へすり替わり、「飛び」が発生して収拾がつかなくなった例です。
ロジカルに説明したあとは相手にイメージを想像させる
CRFで納得した相手をさらにその気にさせる方法があります。
相手の頭の中に具体的なイメージを思い描かせることで、スピーチの効果をさらに高めるのです。
聞き手が結論に理解を示し、賛同させることに成功したとします。
でも、そこで終わってしまっては中途半端です。
そこから、さらに相手の気持ちを自分に向けさせる方法が「頭の中のイメージ」です。
すでに課題に対して賛同している相手ですから、あとは何を求めているのかを考えて、それを具体的にビジュアル化できるように相手を手助けするのです。
そのために有効なアプローチが2つあります。
相手の頭の中でイメージを描いてもらう方法とイメージの中へ聞き手を入れる方法です。
頭の中に描いてもらう方法は、聞き手が興味を持っている対象について具体的な説明をしていくことです。
車の購入を考えているのであれば、その車の外観の美しさ、内装の心地よさ、家族の喜ぶ顔などを思い描かせることになります。
一方、イメージの中へ入れる方法では、実際に運転している状況を想像させます。
オートドライブでのんびり景色を眺める自分、ハイウェイを快適に疾走する自分、恋人や友達を乗せた楽しいひとコマ。
聞き手はより強い興味を持つはずです。
話している自分と相手を俯瞰してみる
自分を主張するだけでは相手を説得できません。
相手の気持ちを理解することも大切です。
俯瞰して自分と相手を見る「メタ認知」を身につけましょう。
スピーチでは、自分の主張を一方的に話しても相手には伝わりません。
相手には相手の考え方や気持ちがあるのですから。
では、どうすれば自分の考えを聞き手に理解してもらえるのでしょう。
まず、最初のポイントは、自分と相手を俯瞰してみることです。
高い離れた場所に視点を移して、自分と聞き手の様子をイメージします。
聞き手から見た自分の姿をチェックして、聞き手の反応に合わせて話し方を変えるなどの工夫ができるようになるはずです。
より具体的な方法として、プレゼンや会議の前に聞き手の席に実際に座ってみるのも効果があります。
聞き手に憑依したつもりで、話し手である壇上の自分の姿をイメージしてつぶさに観察すれば、より客観的にスピーチしている自分自身を理解でき、問題点の修正も容易です。
その上で姿勢や声の高さ、話すスピードなどをリハーサルでチェックしていけば、自分と聞き手の距離は確実に埋まっていきます。
「主観の自分」を意識する「メタ認知」をいつでも考えていきましょう。
根回しやアフターフォローも必要に応じて行うべし!
プレゼンは1回で勝負が決まる場合もありますが、社内会議など前後にフォロー可能な機会があるなら、積極的に活用していきましょう。
ほとんどの場合、聞き手はあなたの話の8割方は理解できていません。
言い換えれば、主張のはっきりした「コアの1分」をしっかり伝えられさえすれば、相手を動かすことは十分可能です。
残りの時間は、その主張を補強し、より相手を動かしやすくするために費やしましょう。
また、プレゼン前後に根回しやアフターフォローする機会があるのなら、その機会をフル活用しましょう。
プレゼン以外にも時間を費やすというデメリットこそあるものの、相手の理解度が深まり動いてくれる可能性が高まるのであれば、徹底的に機会を追求すべきなのです。
SDS法とPREP法
「伝わる話し方」にはパターンが存在します。
その中でも有名なフレームワークが「SDS法」と「PREP法」です。
SDS法は最初と最後にサマリー(※4)を用意して、その間にディテール(※5)を挟む方式です。
最初に全体の概要を話すため、聞き手が以降の話を理解しやすくなり、詳細のストーリー性を強調することで、まとめを補強できます。
公演や製品紹介など、話す時間が長い場面に適した方式です。
一方PREP法は最初にPoint(主張)を述べ、それをReason(根拠)、Example(具体例)で補強する方法です。
SDS法と異なりDetailのストーリー性が不要なため、社内の報告会議やプレゼンなど、時間の短い場面に向いていますが、淡々となりがちなため、場面に応じて使い分けましょう。
新しい取り組みを説明するときのPCSF法
プレゼンのフレームワークは定番のSDS法、PREP法以外に何種類もあります。
ここではそのひとつ「PCSF法」を紹介しましょう。
PCSF法はスタートアップが新しい、革新的な企画を紹介する際に役立つフレームワークです。
最初に現状のProblem(問題)とそれによるChange(変化)を紹介することで聞き手のイメージを促し、以降のSolution(解決策)、Future(未来)の理解度を深めやすくできます。
先に挙げたSDS法、PREP法も含め、良いプレゼントは全て「結論 – 根拠 – 実例」の3段階で構成されています。
話をどう組み立てたら相手を動かしやすくなるのか、流れがスムーズになるのかを意識して、自分でもフレームワークを作成してみると、プレゼンの腕も上達することでしょう。
相手が何を質問しているのかを見つける
会議で意見を求められた途端、頭が真っ白になってしまう。
これを解決するヒントは、相手の質問に隠れています。
用意していた話をするのは問題ないのに、質問された途端焦ってしまうことはないでしょうか。
これは、相手の質問に対して何から答えればいいのか、わからなくなってしまうからです。
この問題は「質問に対する答え方のパターン」を作り、そのパターン通りに頭を働かせることで解決できます。
突然質問されると、早く答えようと焦りがちですが、テストで問題を読まずに答えを書く人はいません。
同じように、まず「何を聞かれているか?」を把握しましょう。
それが理解できたら、その問いに合った答え(主張)を決め、それを補強する根拠と具体例を挙げるだけで立派な回答になります。
話が伝わらなくなる4つのタブー
良い話し方があれば、当然悪い話し方もあります。
ここでは、話が伝わりにくくなる、4つのタブーについて解説します。
最もありがちなのは「自分が頑張ったことの説明」です。
話す側は、いかに苦労したかを盛り込むことで主張の信頼性を高められると思いがちですが、聞き手は早く結論を聞きたいものです。
話に笑いを盛り込むのも、プレゼンの場では相手が白けて逆効果になるケースが多いため、避けたほうが賢明です。
また、会議の参加者全員に気を使いすぎて、何を言いたいのかわかりにくくなってしまう人や、自分の主張のマイナス面を語ってしまう人もいます。
特にビジネスの場では、自分のポジションを明確にし、はっきりと主張することが大事です。
他の人のフォローやマイナス面は添える程度にとどめましょう。
プレゼンもミュージシャンと同じ!ライブでダイブ!
「自分のメッセージを聞き手に伝える」という点で、ライブ中のミュージシャンからビジネスマンが学べる点は多々あります。
プレゼン中、相手はあなたの話だけに集中していることはなく、姿勢や話し方、間の取り方にも注目しています。
これらが欠けていると、いくら話の中身が充実していても、相手はあなたの話に不安を覚えてくることでしょう。
話は伝え方、つまりデリバリーの方法も大事なのです。
ライブ中のミュージシャンが客席にダイブすることがあります。
これは物理的に近づくことで、精神的にも近づく効果があるのです。
プレゼンもこれと同じで、相手の懐に飛び込む姿勢が大事です。
聞き手が観客であるとイメージし、メッセージを届けやすくなる立ち居振る舞いを意識しましょう。
コラム:アンガーマネジメントを身につけよう!
論理的に話すときの敵は自分の感情です。
自分の考えを相手に何としても理解してもらいたいと思うあまり、つい熱が入って早口になったり、焦って肝心なことを説明し忘れたりするのはまだいい方です。
ときにはあなたに意地悪な質問をしたり、あなたの説明を全く聞いていなかったりする人もいるでしょう。
しかし、そういうときに怒ってしまったら、あなたの負けです。
商談はそこで終わってしまいます。
ビジネスパーソンにとって自分の怒りの感情をコントロールすることは必須なのです。
この怒りをコントロールする方法論を、近年ではアンガーマネジメントと呼んでいます。
アンガーマネジメントとは、その名の通り「怒りと上手に付き合う」方法。
自分や他人の「怒り」に振り回されず、「怒り」を上手にコントロールすることで快適な生活やよりよい人生を目指していこうというメソッド。
怒らないことを目指すといった精神修行ではなく、知識と技術を使って「怒り」を取り扱う「スキル」です。
アンガーマネジメントを学ぶことは、ロジカルシンキングに必ず役立つでしょう。
▼こちらもおすすめ▼